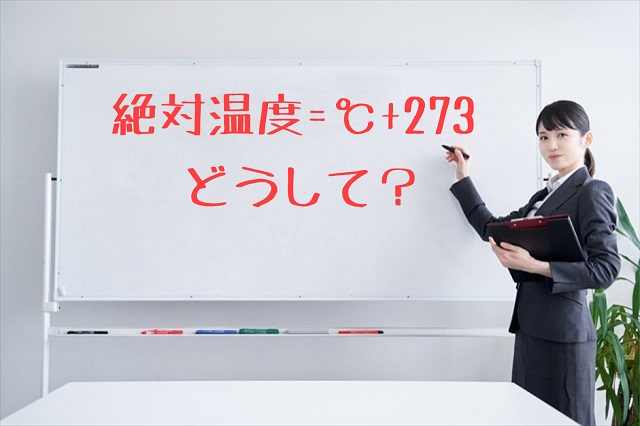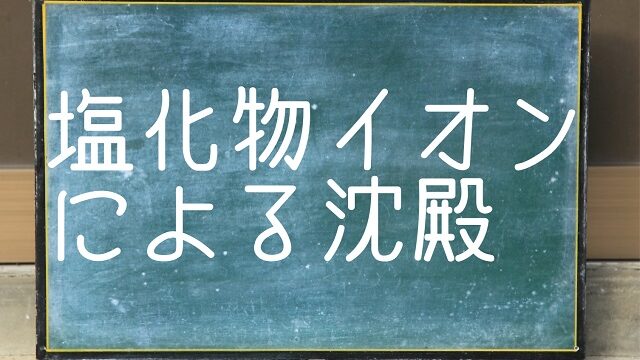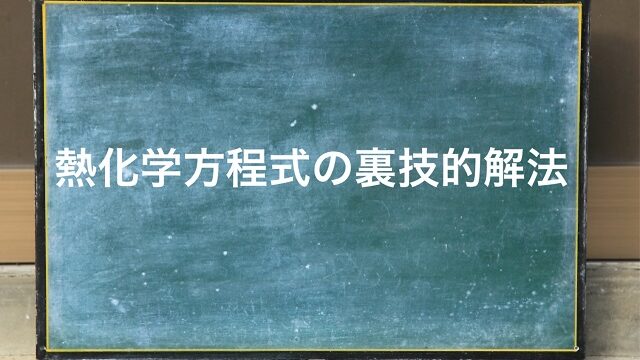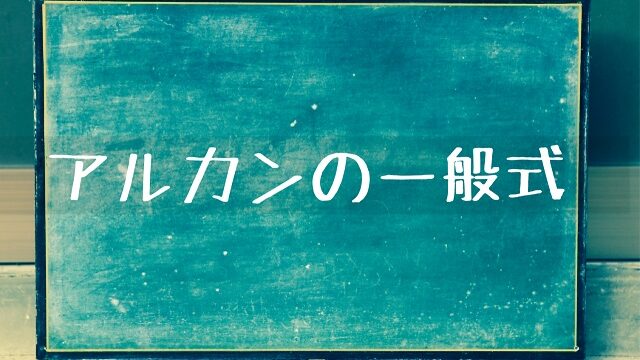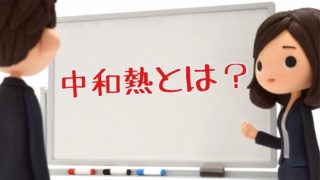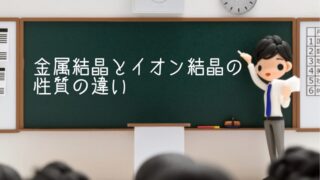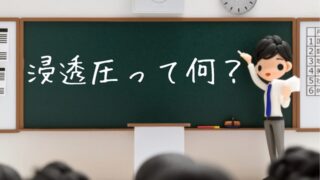前回の記事で
・圧力P(Pa(パスカル)、mmHg)
・絶対温度T(K)
・体積V(L)
・物質量n(mol)
だと解説し、そのあと、圧力の単位であるmmHgの意味について
かなり詳しく解説しました。
⇒mmhgとは?意味を図を使ってわかりやすく解説
今回の記事では絶対温度Tはどうして℃に273を足すのか?
解説したいと思います。
℃+273=絶対温度になる理由
絶対温度において℃にどうして273を足すのか?というと
シャルルという研究者の実験が原点になっています。

シャルルという人は気体の体積と温度の関係を実験的に調べました。
風船を使って温度を1℃上げたら、その風船の体積がどう変化するか調べました。
、
たとえば、0℃のときの体積が水は$V_0 $L(リットル)だったとしましょう。
これが1℃温度が上がると、シャルルの実験によると0℃のときの$\frac{1}{273} $だけ
体積が増えることがわかりました。
つまり、
・0℃⇒$V_0 $(L)
・1℃⇒$V_0 $+$\frac{1}{273} $$V_0 $(L)
ということです。
逆に1℃温度が下がるとどうなったでしょう?
0℃からマイナス1℃になると、$\frac{1}{273} $だけ体積は小さくなることが
シャルルさんの実験によって証明されました。
・-1℃⇒$V_0 $ー$\frac{1}{273} $$V_0 $(L)
・0℃⇒$V_0 $(L)
・1℃⇒$V_0 $+$\frac{1}{273} $$V_0 $(L)
ということがわかったのです。
さらに1℃下がってマイナス2℃になったらどうなるでしょう?
$V_0 $ー$\frac{2}{273} $$V_0 $(L)
となることがわかりました。
・-2℃⇒$V_0 $ー$\frac{2}{273} $$V_0 $(L)
・-1℃⇒$V_0 $ー$\frac{1}{273} $$V_0 $(L)
・0℃⇒$V_0 $(L)
・1℃⇒$V_0 $+$\frac{1}{273} $$V_0 $(L)
つまり、$\frac{1}{273} $$V_0 $だけ、1℃変化するごとに体積が変化していくということです。
1℃低くなれば小さくなるし、高くなれば大きくなります。
$\frac{1}{273} $$V_0 $というのは変化量なわけですね。
ではこのままずっと温度を下げていったとしましょう。
ある温度で気体の体積が0になりますよね。
たとえば、-1℃だと$V_0 $ー$\frac{1}{273} $$V_0 $(L)で
-2℃だと$V_0 $ー$\frac{2}{273} $$V_0 $(L)といった感じで
温度が1℃下がるごとに、$\frac{1}{273} $$V_0 $だけ体積が小さくなっていくわけですからね。
体積は有限なので、どんどん温度が下がればいつかは0になります。
ではいつ0になるでしょう?
$V_0 $ー$\frac{273}{273} $$V_0 $になったら体積は0になりますよね。
$\frac{273}{273} $$V_0 $=$V_0 $なので、
$V_0 $ー$V_0 $=0となりますからね。
つまり、ー273℃という温度で体積が0Lになることが予想できます。
でも、気体の体積が0になるということはちょっと考えられませんね。
なぜならあったものがなくなるわけですからね。
-273℃というのはあり得ない、実現不可能な温度だと
高校化学では教えられます。
なので、-273℃より低い温度は存在しないと考えておいて問題ありません。
-273℃原点とする新しい温度作ろうということになったのです。
これが絶対温度です。
-273℃を0とする温度単位。
だから、℃+273なのです。
そして絶対温度の単位はK(ケルビン)として、
絶対温度(K)=℃+273
ということになりました。
これがシャルルの実験です。
気体の体積の変化から絶対温度が新しく作られることになりました。
以上、参考にしていただければ幸いです。