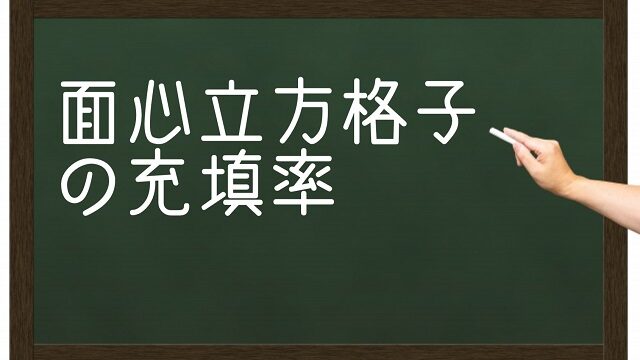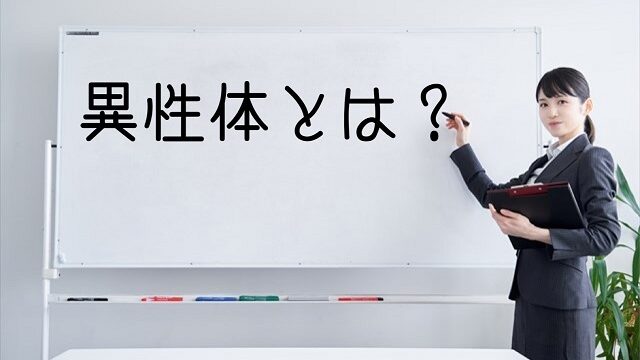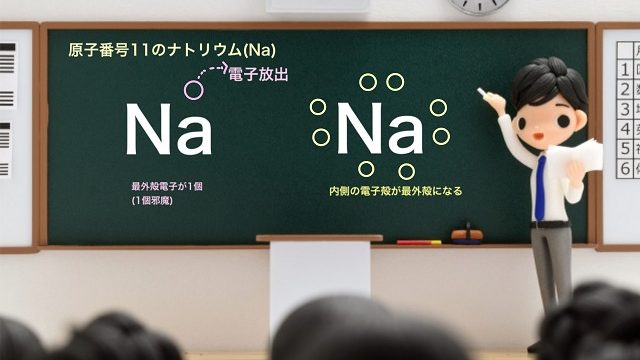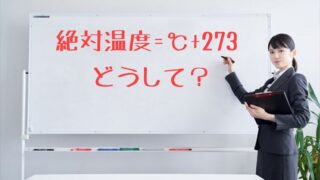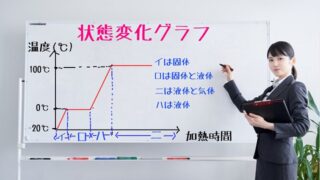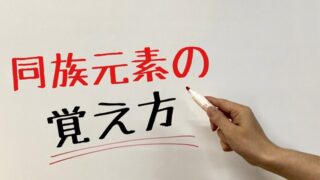・生成熱
・燃焼熱
・溶解熱
について解説しました。
⇒生成熱の定義をわかりやすく解説
⇒燃焼熱とは?わかりやすく解説
⇒溶解熱とは?わかりやすく解説
今回の記事では中和熱について詳しく解説していきます。
中和熱とは?
中和熱とは酸と塩基が中和反応を行って水1モルを生成するときに発生する熱量のことです。
ここで『発生する熱量』と書きましたが、『必ず発熱』します。
・酸
・塩基
が化学反応を起こして
お互いの性質を打ち消しあう反応のことです。
ちなみに酸とか塩基の意味がわからないという方はこちらの記事をご覧ください。
⇒アルカリと塩基の違いをわかりやすく解説
⇒酸とは何?わかりやすく解説
中和反応によって1モルの水ができるときの反応熱が中和熱の定義になります。
中和熱の具体例
中和熱の具体例として以下を挙げておきます。
$H^{+}aq $+$OH^{-}aq $=$H_2O $+56.5KJ
これを見たら、「あ、中和熱だな」と思えるのは
$H_2O $の部分です。
$H_2O $の係数が1となっているところが中和熱を意味しています。
つまり、$H_2O $は1$H_2O $という意味です。
それからaqはアクアと読みます。大量の水という意味です。
$H^{+}aq $+$OH^{-}aq $=$H_2O $+56.5KJ
上記式からわかるように1molの$H^{+}aq $と$OH^{-}aq $から
1molの$H_2O $ができるときに発生する熱量なので、
どんな左辺においてどんな酸なのか、
どんな塩基なのか?によって熱量の大きさは変わりません。
とはいえ、左辺が弱酸であったり弱塩基であったりした場合は
電離するときに吸熱反応を起こします。
だから強酸や強塩基による中和反応よりも
吸熱反応により熱量が減少するため、
熱量が結果的に小さくなることがあることを知っておきましょう。
とにかく中和熱の定義は『水が1モルできるとき』なので、
1$H_2O $というところがポイントなのです。
そして、水が1モルできるときに56.5KJ発生します。
中和熱まとめ
・生成熱
・燃焼熱
・溶解熱
・中和熱
について解説してきました。
⇒生成熱の定義をわかりやすく解説
⇒燃焼熱とは?わかりやすく解説
⇒溶解熱とは?わかりやすく解説
こういうのは名前のついた反応熱なのです。
名前のついた反応熱にはきちんと定義があります。
何を1モルあたりで表現しないといけないか?
みたいな定義があるので、その定義をしっかりと覚えておきましょう。
たとえば生成熱といわれたら
生成物1モルが単体からできるときの熱です。
燃焼熱といわれたら物質1モルが完全燃焼する時の熱です。
溶解熱は1モルの溶質が溶媒に溶けるときのものです。
中和熱だったら中和反応で1モルの水ができるときのものです。
こういう定義をしっかりと覚えておいて
何を係数1にしないといけないか?というのをしっかりと覚えておきましょう。