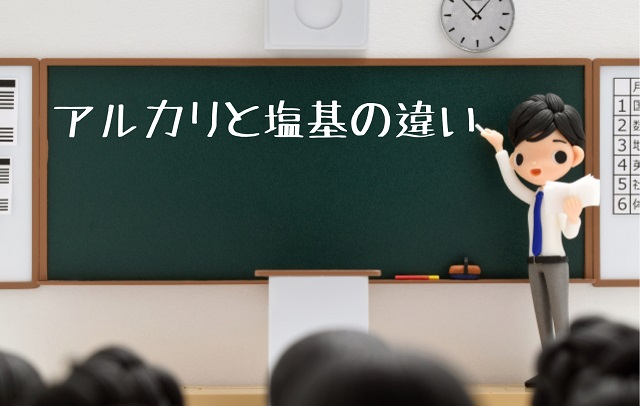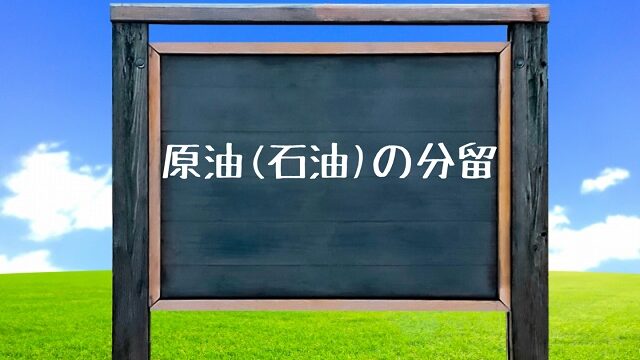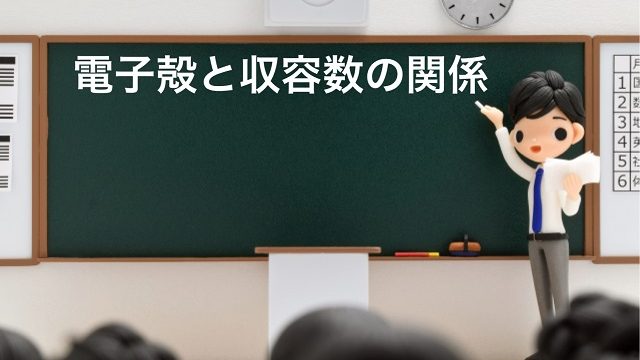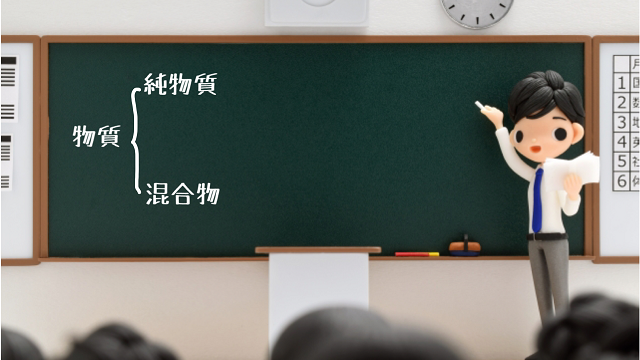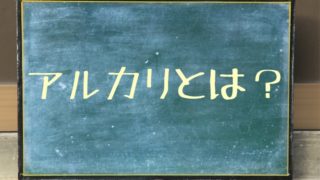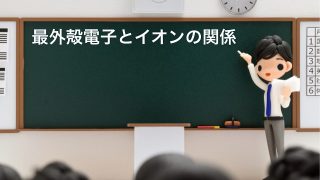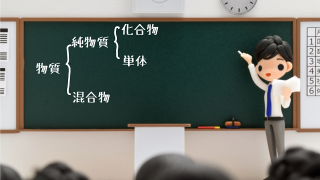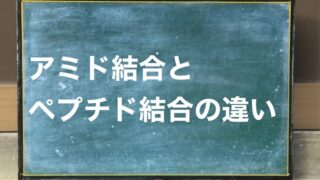前回アルカリとは何か?解説しました。
⇒アルカリとは何か?種類とともわかりやく解説
前回解説したアルカリという用語は高校に入ると、『塩基』と習います。
では、アルカリと塩基ってどう違うのでしょう?
今回の記事ではアルカリと塩基の違いについて解説します。
アルカリと塩基の違い

前回解説したアルカリの記事では水溶液中での話でした。
⇒アルカリとは何か?種類とともわかりやく解説
『水溶液中で』という場合はアルカリです。
水溶液中以外も含めると『塩基』となります。
さらに詳しくアルカリと塩基の違いを説明します。
これ説明できる人はかなり少ないです。
なので、希少な情報なので最後までご覧ください。
まず、塩基(えんき)って何でしょう?
漢字から想像していただきたいのですが、
塩基とは酸と中和して『塩』の『基(もと)』になるもののことです。
酸と中和して塩の基(もと)になるものですから、
固体でも気体でも塩基になりえます。
たとえば、水酸化ナトリウムの固体って空気中の二酸化炭素と中和反応することもできます。
また、アンモニアは気体ですが、
塩酸と中和反応することもできます。
固体や気体も含めて酸と中和して塩の基になるものは全部塩基に該当します。
で、塩基の中の一部分にアルカリという領域があるという感じです。
アルカリというのは酸と中和するものですが、
特に水溶液の状態のものを指します。
・塩基・・・酸と中和して塩の基になるものは全部(固体、液体、気体すべて)
・アルカリ・・・塩基の中でも水溶液の状態のもののこと(固体と気体は含まない)
ということです。
水溶液だったらアルカリといえますが、
そうじゃない酸と反応できるものもあります。
液体以外の固体や気体でも酸と反応できるものも含めて塩基といいます。
前回の記事で解説したアレニウスの定義では『水溶液中で』といっています。
⇒アルカリとは何か?種類とともわかりやく解説
水溶液の状態なのでアルカリと読んでOKです。
だから前回の記事のタイトルは『アルカリとは何か』としたのです。
でも、固体や気体の状態だったらアルカリとは言わず塩基といいます。
以上、塩基とアルカリの違いについて解説しました。
続いて酸や塩基における強弱ってどういうことなのか?
わかりやすく解説していきます。
⇒酸と塩基の強弱って何が違う?