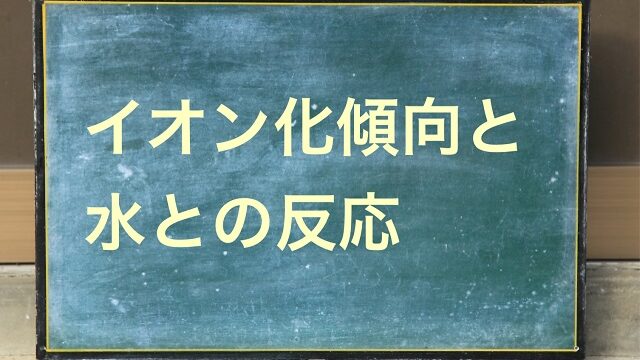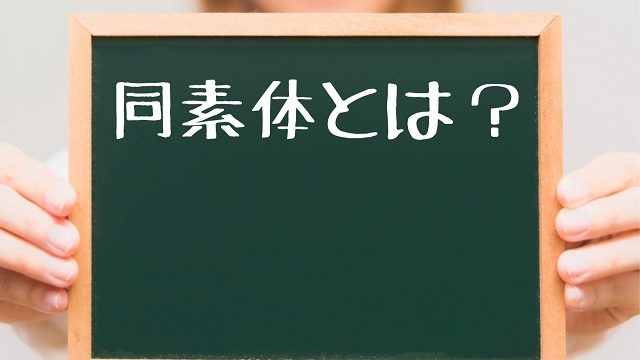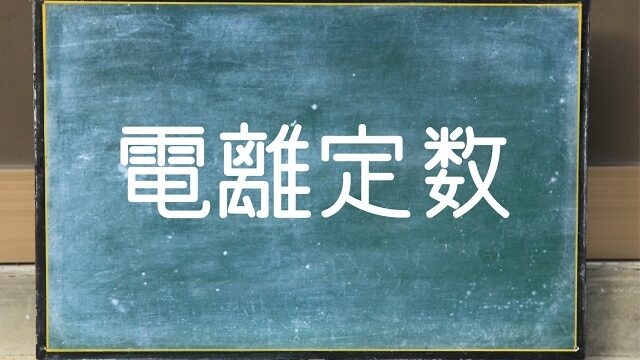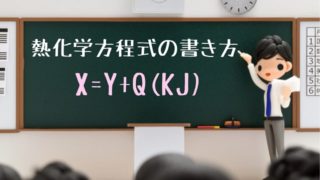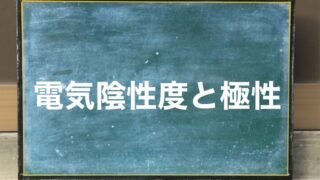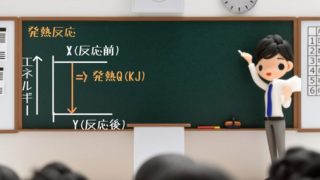前回の記事では熱化学方程式の書き方について解説しました。
⇒熱化学方程式の書き方(ルール)をわかりやすく解説
熱化学方程式の書き方を理解したら
次に生成熱の定義と、実際の書き方を覚えていきましょう。
生成熱を表す式と熱化学方程式を表す式は少し違います。
この違いが分かっていないと大学受験などで苦労する可能性が出てきます。
もしかしたら、生成熱がわからなくて不合格になる可能性もあります。
ですので、今回の記事を最後までご覧いただきたいと思います。
Contents
生成熱の定義

生成熱はどういう反応熱か?という定義が重要です。
定義が分かっていないと方程式を作れませんからね。
生成熱とは1モルの化合物が単体からできるときの反応熱のことです。
ここで、単体とは何のことでしょう?
単体とはもうこれ以上細かい成分に分離できない純物質のことです。
もう少しかみ砕いて説明しますと、単体とは1種類の元素だけでできている純物質のことです。
純物質の意味が分からない方はこちらの記事をご覧ください。
⇒純物質と混合物の違いを例を挙げてわかりやすく解説
生成熱は発熱反応が起こる場合もあれば
吸熱反応が起こることもあります。
⇒発熱反応が発生する身近な例
⇒吸熱反応の身近な例
例を挙げますね。
アンモニアの生成熱は46kJ/mol
です。
『/mol』の部分を赤くしていますね。
これは$NH_3 $1モルあたりという意味です。
アンモニアが1モルできるとき、
46KJ発熱するという意味です。
では実際にアンモニアの生成熱を表す方程式を作っていきましょう。
アンモニアの生成熱を表す方程式の書き方のコツ
生成熱はイコールの右側から書くのがコツです。
=1$NH_3 $(気)
と書き始めましょう。
そして生成熱の定義に『単体からできるとき』がありましたね。
なんでもいいわけではありません。
窒素の単体といえば、$N_2 $。
右辺の窒素の数は1個だから左辺の窒素の数が2個のままだと
数が合わないので、$\frac{1}{2} $$N_2 $(気)と表現します。
$\frac{1}{2} $$N_2 $(気)=$NH_3 $(気)
となります。
方程式は分数を使ってもOKでしたね。
⇒熱化学方程式の書き方(ルール)をわかりやすく解説
それから、アンモニアを見ると水素原子は3つだから$H_2 $が水素の単体なので、
$\frac{3}{2} $という係数が水素の前につきますね。
$\frac{1}{2} $$N_2 $+$\frac{3}{2} $$H_2 $(気)=$NH_3 $(気)
だから上記のようになります。
これでアンモニア1モルが単体からできるときの形を表現したことになります。
ここで$\frac{1}{2} $$N_2 $と$\frac{3}{2} $$H_2 $(気)が単体を意味しています。
1モルのアンモニアが単体からできるときの反応熱なので、
46KJを右辺に付け加えれば完成です。
$\frac{1}{2} $$N_2 $+$\frac{3}{2} $$H_2 $(気)=$NH_3 $(気)+46KJ
これで生成熱を表す熱化学方程式が出来上がりました。
上記式を2倍したものが熱化学方程式になります。
$N_2 $+$3H_2 $(気)=$2NH_3 $(気)+92KJ
となりますね。
くどいようですが、生成熱とは1モルの化合物が単体からできるときの反応熱のことです。
あとちなみになのですが、
単体の生成熱は0KJ/molとして計算しています。
続いて燃焼熱について解説します。
⇒燃焼熱とは?わかりやすく解説