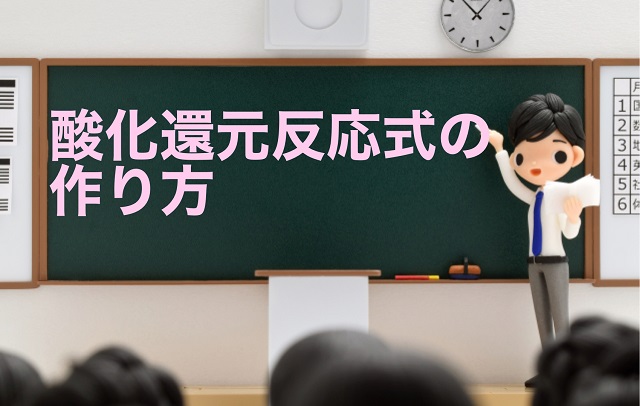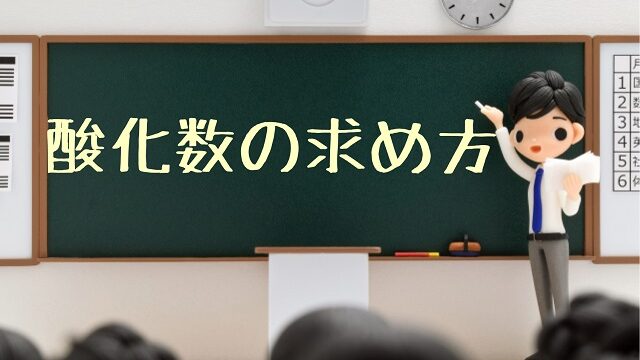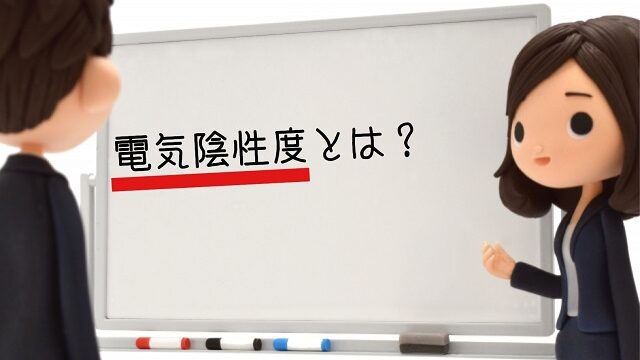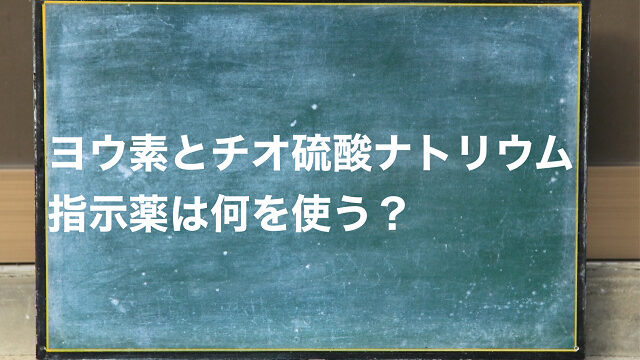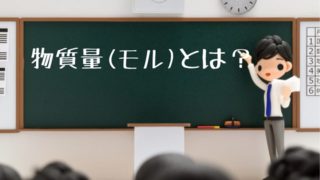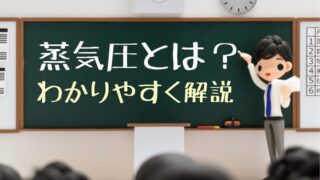今回の記事では
酸化還元反応式の作り方についてわかりやすく解説していきます。
Contents
酸化還元反応式の作り方
以前解説した酸塩基では
pHが計算できれば高校化学だと点数が取れると思います。
⇒pHの計算方法について例題を使ってわかりやすく解説
これに対して酸化還元は?
となると酸化還元反応式の作り方が理解できれば点数が取れるようになると思います。
⇒プロフィールと当ブログを作ることになったきっかけ
最終目標をきちんと頭に入れておきながら
学習を進めていった方が大学受験や定期テストで
いい点数を取りやすくなりますからね。
そこで今回の記事では一番有名な酸化還元反応式を
例にとって解説していきますね。
無名な酸化還元反応式を例に説明しても
点数に結び付きにくいですからね。
過マンガン酸カリウムを例に酸化還元反応式の作り方を解説
過マンガン酸カリウムを例に解説していきますね。
長ったらしい名前ですね。
でも酸化還元反応では超有名ですよ。
酸化還元反応式の過マンガン酸カリウムは
ワンピースでいったらルフィくらいです。
話を元に戻しますね。
まず過マンガン酸カリウム硫酸酸性溶液を用意します。
硫酸を加えたら酸性になりますよね。
硫酸で酸性にしているだけです。
過マンガン酸カリウムが反応するときには
必ず硫酸がお供についているだけです。
逆に過マンガン酸カリウムがいて硫酸がいないのは変な感じがします。
それくらいの感覚でいてくださいね。
滴定するとき、過マンガン酸カリウムは硫酸とセット!
その理由は・溶液が酸性状態のときに酸化剤の機能が強くなる!・硫酸は加熱しなければ酸化剤として働かないから過酸化マンガンの還元を邪魔しない!
こういうぴったりと明確な条件には理由がある、すごく面白い— あったかい肉 (@xiao_BIGLOVE__) November 4, 2022
話を元に戻します。
過マンガン酸カリウム硫酸酸性溶液を用意し
そこにシュウ酸を加えます。
このときの化学反応式を組み立てること。
イコール酸化還元反応式の作り方になります。
これが酸化還元でやらないといけない一番大事なことです。
ステップ(1)半反応式を組み立てる
まず水に溶けて電離して
$MnO_4^{ー} $(過マンガン酸イオン)が電子を取る反応をします。
半反応式で表すと
$MnO_4^{ー} $+8$H^{+} $+5$e^{ー} $⇒$Mn^{2+} $+4$H_2O $
となります。
こちらの記事で過マンガン酸カリウムの半反応式が上記のようになる理由を解説しています。
⇒半反応式の問題を解きながら作り方も覚えよう!
今回の記事では半反応式の作り方については省略します。
上記リンク先で詳しく解説していますからね。
よろしくお願いします。
話を元に戻します。
$MnO_4^{ー} $+8$H^{+} $+5$e^{ー} $⇒$Mn^{2+} $+4$H_2O $
左辺に電子(5$e^{ー} $)がありますね。
電子をもらって反応しているということです。
つまり酸化剤だということです。
そしてお相手のシュウ酸です。
シュウ酸の半反応式は以下の通りです。
$H_2C_2O_4 $(シュウ酸)⇒$2CO_2 $(二酸化炭素)+$2H^{+} $+$2e^{-} $
シュウ酸の半反応式についてもこちらの記事で詳しく解説しています。
⇒半反応式の問題を解きながら作り方も覚えよう!
シュウ酸の場合、反応して電子($2e^{-} $)を出していますから還元剤です。
$MnO_4^{ー} $+8$H^{+} $+5$e^{ー} $⇒$Mn^{2+} $+4$H_2O $
$H_2C_2O_4 $(シュウ酸)⇒$2CO_2 $(二酸化炭素)+$2H^{+} $+$2e^{-} $
の2つの半反応式ができるということです。
半反応式とは電子を含んでいる式のことです。
ステップ(2)イオン反応式を作る(ヒント:電子を消す)
今回の記事は酸化還元反応式の作り方です。
半反応式は通過点にすぎません。
くどいようですが、半反応式の作り方はこちらの記事で詳しく解説しています。
⇒半反応式の問題を解きながら作り方も覚えよう!
$MnO_4^{ー} $+8$H^{+} $+5$e^{ー} $⇒$Mn^{2+} $+4$H_2O $
$H_2C_2O_4 $(シュウ酸)⇒$2CO_2 $(二酸化炭素)+$2H^{+} $+$2e^{-} $
まで作りました。
次は電子を消していきましょう!
$MnO_4^{ー} $+8$H^{+} $+5$e^{ー} $⇒$Mn^{2+} $+4$H_2O $
の電子は5$e^{ー} $であることから5個あるとわかりますね。
$H_2C_2O_4 $(シュウ酸)⇒$2CO_2 $(二酸化炭素)+$2H^{+} $+$2e^{-} $
の場合、電子は$2e^{-} $とあることから2個あるとわかりますね。
なので
$MnO_4^{ー} $+8$H^{+} $+5$e^{ー} $⇒$Mn^{2+} $+4$H_2O $
⇒全体を2倍する。
$H_2C_2O_4 $(シュウ酸)⇒$2CO_2 $(二酸化炭素)+$2H^{+} $+$2e^{-} $
⇒全体を5倍する
[/box04]
では電子を消去していきましょう。
まずは$MnO_4^{ー} $の方、全体を2倍します。
2$MnO_4^{ー} $+16$H^{+} $+10$e^{ー} $⇒2$Mn^{2+} $+8$H_2O $
となりますね。
次に$H_2C_2O_4 $(シュウ酸)も全体を5倍しましょう。
5$H_2C_2O_4 $(シュウ酸)⇒$10CO_2 $(二酸化炭素)+$10H^{+} $+$10e^{-} $
となりますね。
これで
2$MnO_4^{ー} $+16$H^{+} $+10$e^{ー} $⇒2$Mn^{2+} $+8$H_2O $
5$H_2C_2O_4 $(シュウ酸)⇒$10CO_2 $(二酸化炭素)+$10H^{+} $+$10e^{-} $
となり、どちらも電子が10$e^{ー} $と揃いましたね。
電子の数をそろえるのってそこまで理解が難しいわけではないですよね。
電子を消さないと半反応式のままです。
また、酸化還元反応なので電子の受け渡しをやっているわけです。
電子の数をそろえないとおかしいわけです。
だから酸化剤がもらう電子数と還元剤が出す電子数は同じになります。
もし違ったら・・・
「どこからもらってきたんだよ!」とか
「誰からもらったらいいんだよ!」って話になりますよね。
なので酸化剤がもらう電子数、還元剤が出す電子数が同じでないとおかしいわけです。
酸化還元反応は電子の受け渡しなわけですからね。
年貢みたいなものでしょう。
御代官様がもらう年貢とお百姓さんが出す年貢は等しいはずですよね。
誰かが横取りしなければね。
御代官様に年貢を取られるだよ… pic.twitter.com/DmrPSO3X4E
— ゆま@腋教徒(眼鏡主義) (@yuma_extra) November 27, 2021
出す電子数ともらう電子数が等しくないと酸化還元反応だといえませんね。
酸化還元=電子の受け渡し
ですからね。
だから電子の数をそろえるのは当然の話なのです。
話を元に戻します。
(1)2$MnO_4^{ー} $+16$H^{+} $+$10e^{ー} $⇒2$Mn^{2+} $+8$H_2O $
(2)5$H_2C_2O_4 $(シュウ酸)⇒$10CO_2 $(二酸化炭素)+$10H^{+} $+$10e^{-} $
までできました。
2つの式を足し算しましょう。
(1)+(2)をするってことですよ。
注意点は(1)は左辺に$10e^{ー} $があって(2)は右辺に$10e^{ー} $がありますね。
この場合に(1)+(2)をすると$10e^{ー} $は消えますからね。
これは連立方程式のXとかYを消すのと同じことですから理解できますよね。
加減法の話ですよ。
たとえば(2)の右辺にある$10e^{ー} $は左辺に移項したら
マイナス$10e^{ー} $になりますからね。
左辺から右辺、右辺から左辺に移項したら符号が逆になるんでしたね。
移項が理解できない方はこちらをご覧ください。
連立方程式の加減法が理解できない方はこちらの動画が参考になると思います。
話を元に戻します。
(1)+(2)をすることで
2$MnO_4^{ー} $+5$H_2C_2O_4 $+6$H^{+} $⇒2$Mn^{2+} $+8$H_2O $+$10CO_2 $
となります。
この出てきた式はイオン反応式といいます。
ステップ(3)電荷を消して酸化還元反応式完成!
イオン反応式は酸化還元反応式という今回の結論ではありませんよ。
まだ2$MnO_4^{ー} $などイオンがありますよね。
酸化還元反応式に4-とか2+みたいな電荷があってはいけないのです。
化学反応式(酸化還元反応式)では電荷を消す必要があります。
ではどうやって電荷を消すか?
答えはマイナスだったらプラスをぶつけ、
プラスだったらマイナスをぶつけてやればよいのです。
今回の例は過マンガン酸カリウムでした。
2$MnO_4^{ー} $にカリウムのKが入ってませんね。
そこでプラスの$K^{+} $(カリウムイオン)をぶつけてやればよいのです。
2$MnO_4^{ー} $の係数は2なので2$K^{+} $をぶつけましょう。
ただ左辺だけに2$K^{+} $をぶつけるのはダメです。
これは方程式がわかっていたらわかりますよね。
両辺に2$K^{+} $をぶつけてください。
また、左辺には6$H^{+} $があります。
例題では何を使って酸性にしてました?
硫酸を使ってましたよね。
なので6$H^{+} $の正体は硫酸だったのです。
6$H^{+} $の電荷を消すために$SO_4^{2ー} $は3つ必要ですね。
プラスが6個あるので2-が3つあれば消せますね。
硫酸は2価ですからね。
もちろん両辺に3$SO_4^{2ー} $を加えてくださいね。
釣り合わなくなりますからね。
2価とか1価というのは価数の話です。
価数がわからない方は以下の記事を参考にしてみてください。
・両辺に2$K^{+} $を加える
・両辺に3$SO_4^{2ー} $を加える
となります。
するとどうなるでしょう?
2$MnO_4^{ー} $+5$H_2C_2O_4 $+6$H^{+} $⇒2$Mn^{2+} $+8$H_2O $+$10CO_2 $
は
2$KMnO_4 $+5$H_2C_2O_4 $+3$H_2SO_4 $⇒2$MnSO_4 $+8$H_2O $+$10CO_2 $+$K_2SO_4 $
となります。
最後の$K_2SO_4 $ってよく忘れますから気をつけてくださいね。
両辺に同じものを加えれば忘れませんからね。
これで完成です。これが化学反応式(酸化還元反応式)です。
2$KMnO_4 $+5$H_2C_2O_4 $+3$H_2SO_4 $⇒2$MnSO_4 $+8$H_2O $+$10CO_2 $+$K_2SO_4 $
です。
以上のように3ステップを順番に
落ち着いてやっていけば化学反応式(酸化還元反応式)を作ることができます。
以上で解説を終わります。