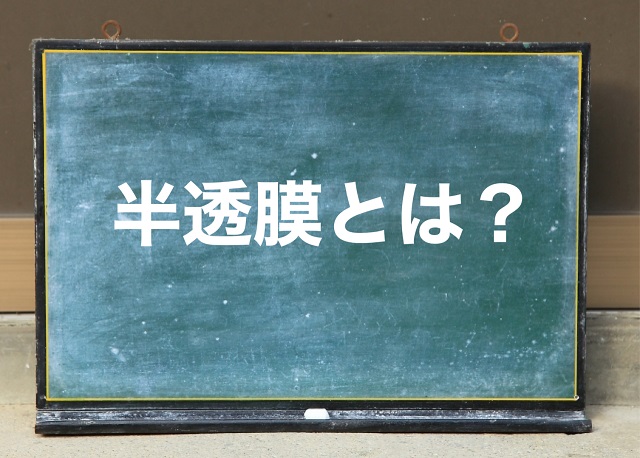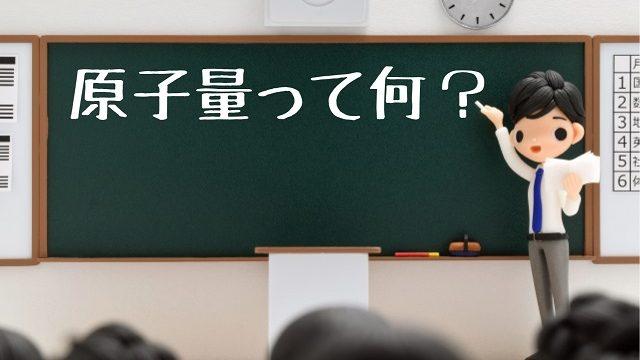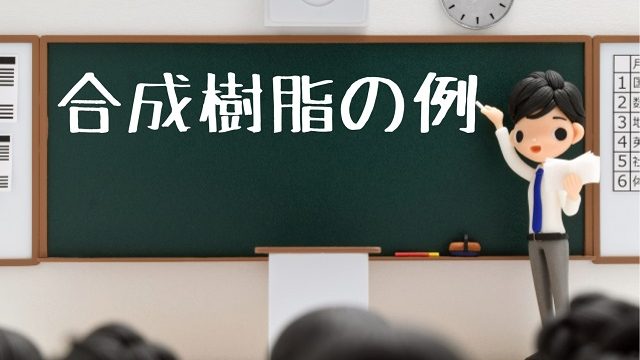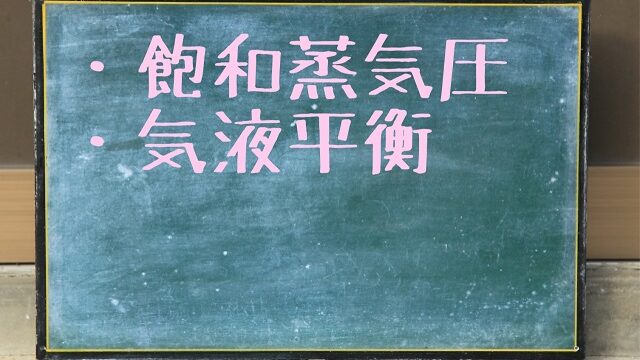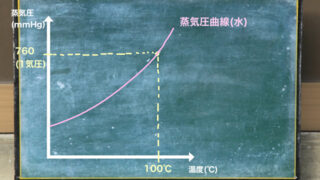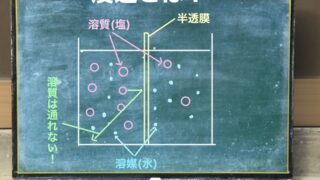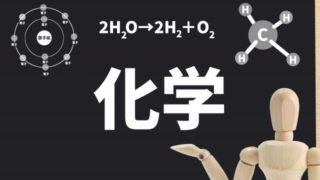今回の記事では半透膜とは何か?全透膜と比較しながら
わかりやすく解説していきます。
Contents
半透膜とは?わかりやすく説明
・半透膜(はんとうまく)
・全透膜(ぜんとうまく)
という膜があります。
性質によって2種類を使い分けています。
半透膜というのは溶質(塩とか)は通れないけど、
溶媒(水など)だけは通れる膜のことです。
溶質とか溶媒とは何か?についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
⇒溶媒・溶質・溶液の違いをわかりやすく例を挙げて解説
だから半透膜の場合、通過できるものは溶媒のみ(水など)ということで
ある意味、半人前の膜だから半透膜という理解でよいでしょう。
あるいは半分だけ通れる(塩などの溶質は通れないけど、水などの溶媒は通れるから)半透膜です。
『半』分だけ『透』過できるから半透膜です。
これに対して全透膜は溶質(塩)も溶媒(水)も両方通ります。
『全』部『透』過するから全透膜です。
次の記事で浸透圧について解説しますが、
浸透圧は半透膜の性質を利用して考えることになります。
なので、半透膜の性質をよく覚えておいてくださいね。
半透膜は溶媒(水)は通すけど、溶質(塩など)は通さない膜のことでしたね。
半透膜と全透膜の具体例
半透膜と全透膜の具体例をご紹介します。
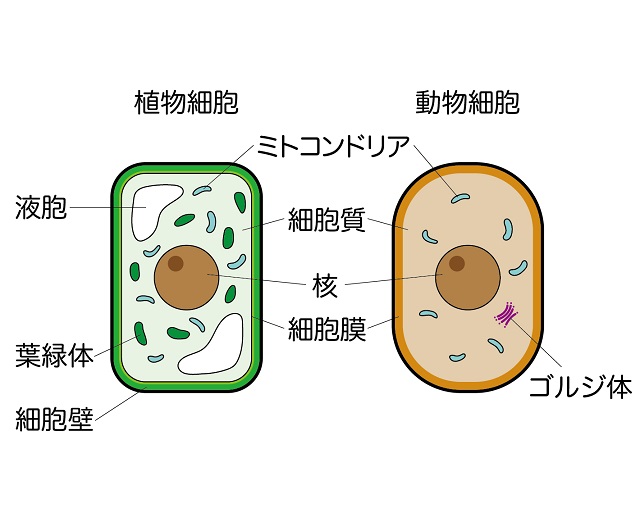
・細胞膜
・セロハン膜
などがあります。
特に細胞膜ですが、すべての細胞の表面には
動物、植物問わず、薄い細胞膜という膜があるのですが、
細胞膜は半透性を持っています。
なので、細胞膜は半透膜の具体例になります。
・細胞壁
・ろ紙
があります。
|
|
ろ紙は上記画像のようなものです。
化学の実験で使います。
ろ紙は全透膜なので溶媒も溶質も両方通します。
わかりやすくいうと
食塩水を入れるとそのまま通るってことです。
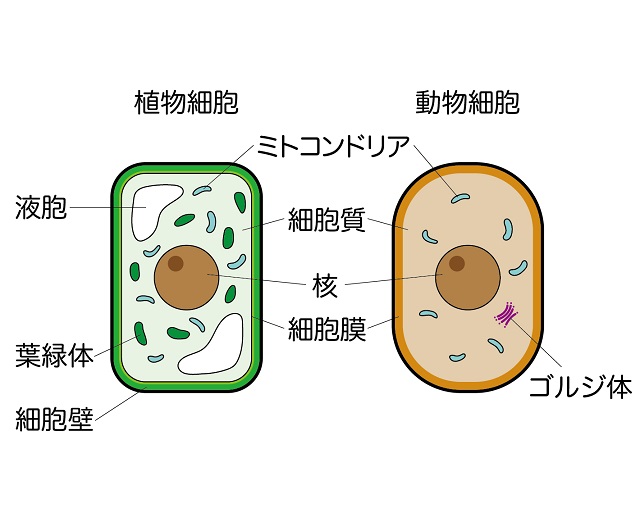
細胞壁は植物細胞だけが持つ硬いものです。
植物の細胞に見られます。
動物の細胞は細胞膜「だけ」で表面が覆われています。
でも、植物の細胞は細胞膜ももちろんありますが、
細胞膜の外側に鎧みたいな硬いものがあります。
これが細胞壁です。
細胞壁は全透性を持っているので溶媒も溶質も関係なく通します。
次の記事では浸透圧について解説しますので
特に半透膜についてよく理解しておいてくださいね。
以上で解説を終わります。