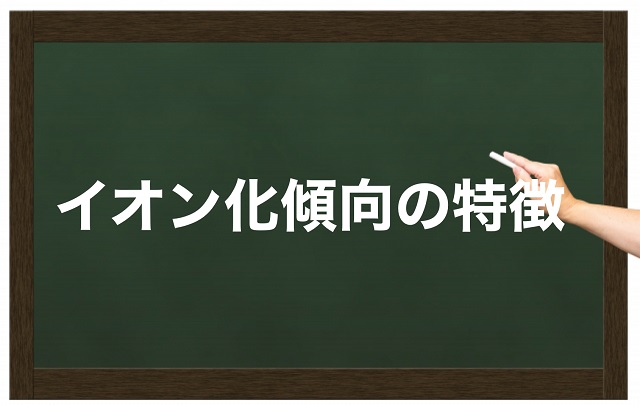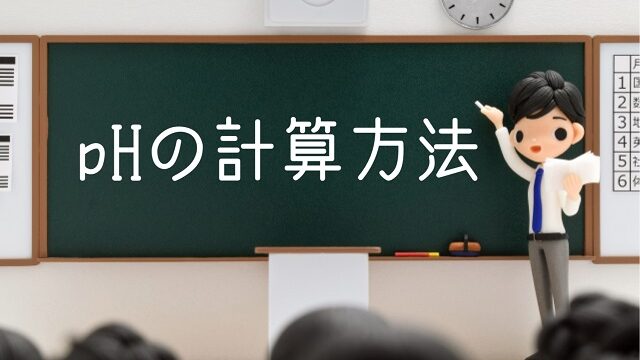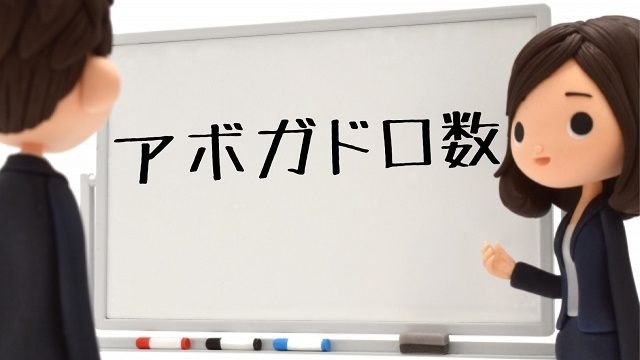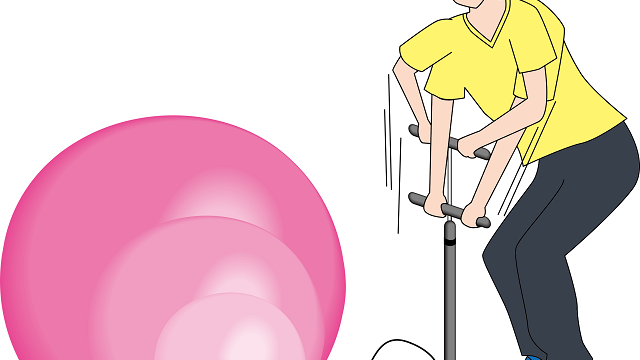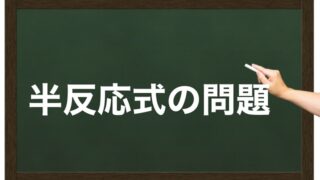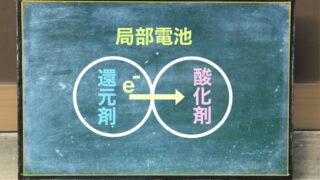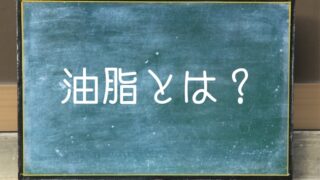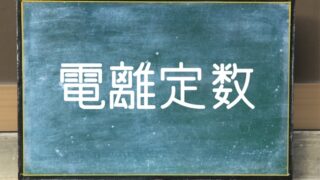今回はイオン化傾向の特徴について解説します。
ちなみにこの記事で解説するイオン化傾向はショッピングモールのイオンが増える話ではありません(苦笑)。
今回解説するイオン化傾向は金属のイオン化傾向です。
【イオン化傾向】
イオン化傾向とはイオン化(電子を放出してプラスの電荷を持った陽イオン):(金属イオン)になる傾向を表したものです。pic.twitter.com/dPo5m7fOgU— 未知なる人間、遥かなる宇宙🌤️ (@Orion_G7) March 9, 2022
Contents
イオン化傾向の特徴
イオン化傾向とは?
金属がどんな反応をするのか?
バカ暗記していませんか?
バカ暗記は受験のときに、緊張感から度忘れしてしまいますよ。
理解して覚えた方がよいです。
そのためにイオン化傾向の理解は非常に重要になってきます。
イオン化傾向っていうのは金属が酸化されやすい順番に左から並べたものです。
【イオン化傾向】
イオン化傾向とはイオン化(電子を放出してプラスの電荷を持った陽イオン):(金属イオン)になる傾向を表したものです。pic.twitter.com/dPo5m7fOgU— 未知なる人間、遥かなる宇宙🌤️ (@Orion_G7) March 9, 2022
どういう順番なのか?並び順に関しては
以下の語呂で覚えましょう。
ここは絶対暗記です。
リッチ(Li:リチウム)で貸そう (K:カリウム) か (Ca) な (Na) 、ま (Mg:マグネシウム) あ (Al) あ(亜鉛:Zn)て(鉄:Fe)に (Ni:ニッケル) すん (Sn) な(鉛:Pb)、ひ (H) ど(銅:Cu)す(水銀:Hg)ぎる(銀:Ag)借(白金:Pt)金(金:Au)
【イオン化傾向の覚え方(強化版)】
Li K Ca Na Mg Al Mn Zn Fe Cd Ni Sn Pb H2 Sn2+ Cu Fe2+ 2Hg Ag Pt Au理系かな?曲がるもん敢えて過度にすんな、卑賤に土手にて杉田借金
(意味不明)※鉄(Ⅱ)イオンは優先度高い
※Hgは[Hg-Hg]2+になる時はAgよりも還元力が高く、Hg2+になる時はAgよりも弱い— Niche(ないちゅ) (@IAA_Loomy) February 19, 2022
イオン化傾向は左から順番に酸化されやすい順番に左から並べたものです。
金属の酸化されやすさを表すものです。
酸化されやすい=陽イオン化しやすさ
という意味でもあります。
金属、たとえばですが、
$Na $単体だったものが$Na^{+} $という陽イオンになるとき、
酸化数が0から+1に増えます。
酸化数が増加するということは酸化されるということですね。
酸化数、Hは1、Oは-2
単体の原子は0
単原子イオンを構成する原子の酸化数はそのイオンの電荷の符号と価数に等しい
化合物中の各原子の酸化数の総和は0だから、HとOの数に気を付ければ全部わかるってことだやっと理解したやったね勝確だ!!YouTubeみる!!!()— (荒川)彗(ボブ限界信者は空を往く) (@keisky119) March 8, 2022
金属単体($Na $)が陽イオン($Na^{+} $)になるときは酸化されたことになります。
だから酸化されやすい金属というのは陽イオン化しやすい金属と同じことです。
なので
金属が陽イオン化しやすい(酸化されやすい)順番に左側から並べたもののこと。
です。
イオン化傾向は金属の反応を考えるのに重要なキーワード
イオン化傾向とは金属の反応を考えるために重要です。
特に電池や電気分解なんかでイオン化傾向の知識・理解はマストになってきます。
金属の反応におけるキーワードは『陽イオン化すること=溶けること』です。
中学校でイオン化傾向を習うと思いますが、
このとき、「イオン化傾向は溶けやすい順番に並んでいる」と教えているようです。
卑)K>Ca>Na>…
Zn(亜鉛)>…Cu(銅)(貴イオン化傾向大→溶けやすい
屋根が銅板ならば
樋は(貴)金箔⁉︎— ニコちゃんまん100% (@tasto519) July 4, 2020
たとえば、銀は濃硝酸に溶けますが、
銀が溶けた=濃硝酸の中で銀イオンになったということです。
鉄くぎが塩酸に溶けますが、
鉄が塩酸の中で鉄イオンになって溶けたということです。
金属が水溶液中で陽イオンになると
その水溶液に溶け込んだことになります。
ここ大事ですよ。
つまり、『陽イオン化すること=溶けること』です。
『陽イオン化すること=溶けること』ということがわかっていれば
金属の反応はすごく理解しやすくなりますよ。
変化後がどうなるか?見えやすくなりますから。
では具体的にいったいどんな反応をするのか、考えていきましょう。
イオン化傾向を使って金属の反応を見ていきましょう。
リチウム(Li)から金(Au)までイオン化傾向を左から順にすると以下のようになります。
Li、K、Ca、Na、Mg、Al、Zn、Fe、Ni、Sn、Pb、H、Cu、Hg、Ag、Pt、Au
イオン化傾向の特徴(水との反応)
イオン化傾向の特徴(冷水との反応)
まず冷水との反応を考えていきましょう。
冷水=熱してない水ですよ。
熱湯や水蒸気は後で解説します。
水と金属って反応するのでしょうか?
反応しないような気がしませんか?
たとえば、鉄を水に入れても反応しませんよね。
時間がたったら錆びるかもしれませんが。
でも、Li、K、Ca、Naみたいなイオン化傾向が左側の金属だと反応性が高いので
水と反応します。
【今日の受験化学知識】
イオン化傾向と金属単体の反応性は合わせて覚えよう。イオンになりやすい=電子を出しやすい=還元剤になりやすいから、左側ほど反応性が高い! pic.twitter.com/4XRh0ecpv7— 受験メモ山本@教育系YouTuber (@jukenmemo) May 23, 2021
Li、K、Ca、Na(リチウムからナトリウムまで)は
冷水とも激しく反応し、$H_2↑ $が発生する。
(↑は気体が発生することを示す)
【Naと水の反応】
金属ナトリウムを水に濡らしたろ紙の上に落とすと黄色の炎を上げながら激しく反応するよ!発生した水素に引火し、軽い爆発も…
2Na+2H2O→2NaOH+H2
NaOHより、フェノールフタレインを入れると赤く!pic.twitter.com/mRn9y7kNhP— 実験たん (@Experiment_tan) March 7, 2022
もんじゅは本当にやばいんだよね
冷却材として使われている金属ナトリウムが空気に触れれば高温で燃焼し、水に触れれば大爆発しちゃう代物で、どうやって廃炉にすればいいのかわからないような状態
大爆発なんてことになったら人類滅亡級の深刻な大惨事だよ
こんな物抱えて核武装とかマジ狂ってるよな— 夜風 (@nocturnospirito) March 6, 2022
爆発的にナトリウムやカリウムといったアルカリ金属やアルカリ土類金属は
火花を出しながら反応していきます。
水素以外の1族の元素を[ アルカリ金属 ]という。
★選択肢について
1族はアルカリ金属
2族はアルカリ土類金属
17族はハロゲン
18族は希ガスです。— 高校化学 無機化学bot 大学受験 大学入試アプリ (@kagaku_m_test) March 9, 2022
なので、水と接触すると非常に危険です。
だから、ナトリウムみたいなアルカリ金属とかアルカリ土類金属は
石油の中で保存します。
石油の中であれば水と接触しませんからね。
カリウムやナトリウムはアルカリ金属と呼ばれ、いずれも密度は1g/cm^3より小さく軟らかい。これらの金属は化学的に活性であり、空気中で直ちに酸素と反応して酸化物となり、また水に入れると水素を発生して溶け、塩基性の溶液になる。この為、カリウムやナトリウムは石油中に保存される。
— 化学知識ボット (@kagakutisiki) March 7, 2022
Q.ナトリウムはどこに保存する?
A.石油中
— にしむぅbot(無機化学1問1答) (@246_bot) March 8, 2022
ナトリウムを扱う化学工場が火災を起こすと
水をかけれません。
水をかけると、また爆発してしまいますからね。
【日本人達がそろそろ忘れている事】
天津で「ナトリウムを蓄積している場所」で火事が起きて、中国の消防は水を掛けて鎮火しようとして大爆発した事件(👃ホジ#基礎化学 https://t.co/rePCKZvKl5— 💙🐱夢猫😷 (@masaharu19759) March 3, 2022
こんな感じでナトリウムは反応性の高い危険な金属です。
イオン化傾向の特徴(熱湯との反応)
Li、K、Ca、Na、Mg(リチウムからマグネシウムまで)は
熱湯と反応し、$H_2↑ $が発生する。
(↑は気体が発生することを示す)
当然かもしれませんが、冷水と反応する金属は熱湯とも反応します。
なので冷水で反応したリチウムからナトリウムまでだって熱湯と反応します。
ここでは冷水には反応しなかったマグネシウムが熱湯であれば反応するというところが大事です。
だからマグネシウム以上は熱湯と反応して$H_2↑ $が発生するということです。
イオン化傾向の特徴(高温の水蒸気との反応)
イオン化傾向が鉄以上の金属は高温の水蒸気となら反応できます。
Li、K、Ca、Na、Mg、Al、Zn、Fe(リチウムから鉄まで)は
高温の水蒸気と反応し、$H_2↑ $が発生する。
(↑は気体が発生することを示す)
だからアルミニウムとか亜鉛とか鉄は高温の水蒸気とでないと反応しません。
もちろん、それ以上のもの(Li、K、Ca、Na、Mg)は
高温の水蒸気と当然反応します。
イオン化傾向が右に行けば行くほど、
反応性が落ちていくイメージを持つと理解しやすいと思います。
たとえばマグネシウムだったら熱湯より高温でないと反応しませんし、
アルミニウムや亜鉛や鉄は高温の水蒸気でないと反応が起こりません。
それ以下(Ni、Sn、Pb、H、Cu、Hg、Ag、Pt、Au)になると
水とは反応が起こりません。
どんな温度でも水と反応することがありません。
これが金属と水との反応になります。
温度によって反応が起こるかどうか変わってきますが、
左側に行くほどより低温でも反応できるということです。
【化学】
金属の反応性を覚えるのは大変ですね💦「イオン化傾向」を「イオンになりやすい・単体になりにくい」と解釈し、イメージをつかもう!相手が空気でも水でも酸でも、とにかくイオン化傾向が高い程反応性が高くイオンになりやすいのです。
各知識がばらばらにならないようまとめて覚えよう! pic.twitter.com/RbeCkzaJet
— S3 Medical|医学部・東大専門予備校 (@S3_Medical) February 15, 2022
イオン化傾向の特徴(水と反応すると水素が発生する理由)
ここで、疑問に感じた方、いませんか?
水系統と反応すると、とりあえず$H_2↑ $が反応しましたよね。
どうして$H_2↑ $ができるのでしょう?
$Na $+$H_2O $
ナトリウムと水の反応で考えてみましょう。
ナトリウムは冷水とも激しく反応しますよね。
ここは復習ですからね。
$H_2O $(水)はごくわずかですが、$H^{+} $(水素イオン)と$OH^{ー} $(水酸化物イオン)に
イオン化しています。
ナトリウムという金属はイオン化傾向は水素よりも大きい(左側)ですよね。
金属の比重が4より小さいモノを軽金属、4よりも大きいモノを重金属と呼んでいる。
イオン化傾向
物質相互を相対的に酸化のしやすさ順に並べたモノである(偶に出題されます)
Li<Cs<K<Ba<Ca<Na<Mg<Al<Zn<Fe<Ni<Sn<Pb<H<Cu<Hg<Ag<Pt<Au— cyberぺづ (@poissonfille) March 8, 2022
つまり、水素よりもナトリウムの方が、
はるかに陽イオンになりやすい金属なわけです。
だから、$Na $と$H^{+} $で陽イオンの入れ替えが起こることになります。
なので単体の$Na $は$Na^{+} $となり、$NaOH $(水酸化ナトリウム)という化合物ができます。
そして$H^{+} $だったものは単体の$H_2 $に戻るのです。
係数に注意してください($\frac{1}{2} $$H_2 $となります)。
$Na $+$H_2O $⇒$NaOH $+$\frac{1}{2} $$H_2↑ $
以上のような理屈で水素ガスが発生しているわけですね。
これは他の金属でも同じです。
マグネシウムでも鉄でも水素よりもイオン化傾向が大きいので
水の$H^{+} $と金属の間で陽イオンの入れ替えが起こるので
同じ感じで$H_2↑ $という気体が発生しているわけですね。
水素より左側→酸に溶けてイオンとなり、水素ガス発生。
水素より左側→イオン化傾向が小さい。つまり、酸化力を持たない酸には溶解しない。— ぼっとっと (@rad1rad2_bot) May 13, 2011
イオン化傾向が水素よりも小さい金属は水溶液の電気分解で純金属が析出するのだ。水素よりも陽イオンになり易い金属塩の水溶液を電気分解すると水素ガスが析出。
そういう金属を得たい場合には溶媒を工夫すると良い。ありがちなのは溶融塩。 https://t.co/mo0uZNlDAv
— 窪田 敏之(料理と科学好きで口が悪い歯医者)コロナ流行中は実名で (@QuickToshi) October 3, 2021
イオン化傾向の特徴(酸との反応)
Li、K、Ca、Na、Mg、Al、Zn、Fe、Ni、Sn、Pb、H、Cu、Hg、Ag、Pt、Au
酸との反応では水素がポイントになってきます。
どうして金属ではない水素がイオン化傾向の表に入り込んでいるのでしょう?
酸との反応を理解してもらうためです。
イオン化傾向が水素より大きい金属と小さい金属で反応の仕方が
ガラッと変わってきます。
まずはイオン化傾向が水素よりも大きい金属との酸の反応から見ていきましょう。
イオン化傾向が水素より大きい金属との酸の反応
Li、K、Ca、Na、Mg、Al、Zn、Fe、Ni、Sn、Pb、H、Cu、Hg、Ag、Pt、Au
【イオン化傾向】
イオン化傾向とはイオン化(電子を放出してプラスの電荷を持った陽イオン):(金属イオン)になる傾向を表したものです。pic.twitter.com/dPo5m7fOgU— 未知なる人間、遥かなる宇宙🌤️ (@Orion_G7) March 9, 2022
イオン化傾向が水素よりも大きい金属は酸化力のない酸にも溶け、
$H_2↑ $が発生するという特徴があります。
ところで酸化力がない酸ってどんなものでしょう?
ちなみに酸化力と酸性はまったく意味が違います。
・酸化力は相手から電子を奪う働きのこと
・酸性とは水素イオンを出す働きのこと
です。
では酸化力がない酸ってどんなものがあるでしょう?
電子を奪うことはできないけど、水素イオンを出せるものが該当します。
前回の記事で解説した熱濃硫酸、濃硝酸、希硝酸の3つは
電子を奪うこともできる酸で酸化力がある酸です。
⇒前回の記事はこちら
これ以外の酸が酸化力のない酸です。
たとえば、塩酸($HCl $)や希硫酸(希$H_2SO_4 $)などが酸化力のない酸です。
こちらの反応をご覧ください。
$Zn $+希$H_2SO_4 $
亜鉛と希硫酸の電離で生じる水素イオン($2H^{+} $)の間で
陽イオンの入れ替えが起こります。
さっき解説したように$Zn $の方が水素イオンより
陽イオンになりやすいですからね。
水素よりも亜鉛の方がイオン化傾向が左側だからです。
同時に$An $が$Zn^{2+} $となって$SO_4^{2ー} $と結びつきます。
そして$2H^{+} $が単体に戻り$H_2 $
よって、
$Zn $+希$H_2SO_4 $⇒$ZnSO_4 $($Zn^{2+} $、$SO_4^{2ー} $となっている)+$H_2 $↑
という形で水素ガスが発生します。
このとき、亜鉛は陽イオン($Zn^{2+} $)になり溶けています。
同様に鉄でもアルミニウムでも同じ反応が起こります。
ただ例外的に鉛は塩酸、希硫酸には溶けません。
硝酸には溶けます。
イオン化傾向が水素より小さい金属との酸の反応
Li、K、Ca、Na、Mg、Al、Zn、Fe、Ni、Sn、Pb、H、Cu、Hg、Ag、Pt、Au
イオン化傾向が水素より小さい金属は銅、水銀とか銀です。
銅、水銀、銀という三種類の金属は酸化力のない酸には溶けません。
なぜなら、$H^{+} $と銅、水銀、銀の間で陽イオンの入れ替えは起こりません。
銅の方が水素イオンより陽イオンになりにくいからです。
では酸に溶けないのでしょうか?
溶けることがあります。
特殊能力を持った酸に溶けることがあるのです。
銅、水銀、銀の3種類は
酸化力のある酸には溶けます。
酸化力のある酸って何でしょう?
酸化力のある酸は半反応式で登場する酸です。
⇒酸化剤と還元剤語呂を使った覚え方
・熱濃硫酸
・濃硝酸
・希硝酸
の3種類が該当します。
これら3つの酸化力を持つ酸だと銅、水銀、銀の3種類は溶けます。
ではどうして酸化力のある酸には溶けるのでしょう?
酸化力のある酸(濃硫酸など)は電子を奪う働きを持っています。
銅原子から電子を奪ったら銅イオンになります。
$Cu $⇒$Cu^{2+} $+$2e^{-} $
となりますね。
あるいは銀原子から電子が奪われたら銀イオンになりますね。
$Ag $⇒$Ag^{+} $+$e^{-} $
となります。
ところで、酸化力のある酸と銅や銀の反応で$H_2 $↑は発生しません。
なぜ$H_2 $↑はできないのでしょう?
水素イオンと反応しているわけではありませんからね。
では何が発生するのでしょう?
それは熱濃硫酸、濃硝酸、希硝酸が電子を奪った後、
何になるかで決まります。
これは暗記事項でしたね。
こちらの記事で解説しています。
⇒酸化剤と還元剤語呂を使った覚え方
⇒半反応式の問題を解きながら作り方も覚えよう!
熱濃硫酸なら電子を奪ったら$SO_2 $(二酸化硫黄)になります。
濃硝酸なら電子を奪ったら$NO_2 $、希硝酸なら$NO $になります。
で、イオン化傾向が一番小さい、Pt(白金)とAu(金)ですが、
これら2つは酸化力のある酸でも溶かすことができません。
Pt(白金)とAu(金)を溶かす液体は1つだけです。
王水だけです。
王水というのは錬金術師といわれる人たちが発見したといわれている特殊な液体です。
金をも溶かす液体で、王様の水で王水です。
王水は濃硝酸と濃塩酸を1対3の比率で混ぜたものです。
【金】
イオン化傾向が最も小さく、反応性がとても低いです
しかし極めて強い酸化作用を持つ王水(濃塩酸3:1濃硝酸)にはテトラクロロ金(Ⅲ)イオンになり溶けることが可能です…!
Au+NHO3+4HCl→H[AuCl4]+2H2O+NOpic.twitter.com/b3we7AHEhX— 実験たん (@Experiment_tan) February 26, 2022
本日の豆知識 #理科サークル
塩酸と硝酸を体積比で3:1で混ぜてできる王水は強い酸化力があるため、イオン化傾向が最も小さい金を溶かすことはできるけれども、銀は溶かせない。
なぜなら、銀の表面に塩化銀(水に溶けにくい物質)が発生するため、銀が保護されるためである。 pic.twitter.com/MhXM1dS6jA— インカレサークル:理科サークル (@CqHC4V2eTEPDU6f) September 6, 2020
錬金術師って安い金属から金を作ろうとした人たちです。
でも当時の技術では錬金術というのは失敗に終わりました。
ただ、いろんなことをやっているうちに
いろんな薬品の開発というのは行われていました。
王水もそうです。
ちなみに熱濃硫酸も錬金術師が見つけたといわれたといわれています。
結局、錬金術は不可能でしたが、
科学技術の発展には大きな貢献をしています。
錬金術師はその後、薬剤師になったという説もあります。
錬金術師は薬剤師の前身と言われています。冷凍ご飯を錬金しました。
— T.Yamato (@teiyamato) November 14, 2017
以上でイオン化傾向の特徴についての解説を終わります。