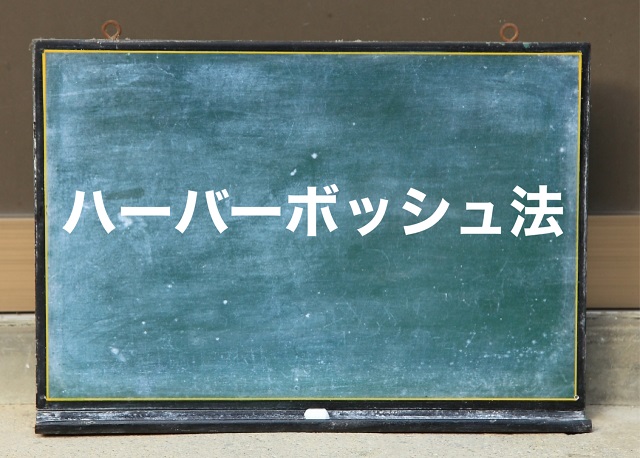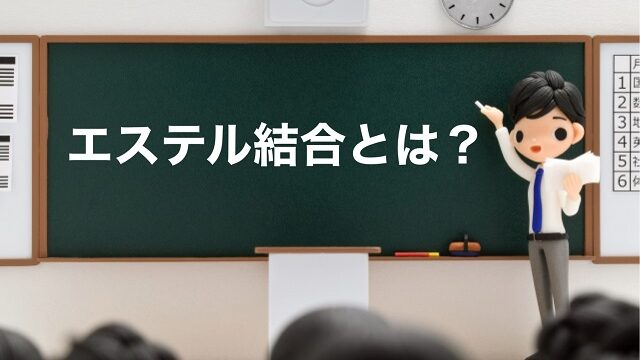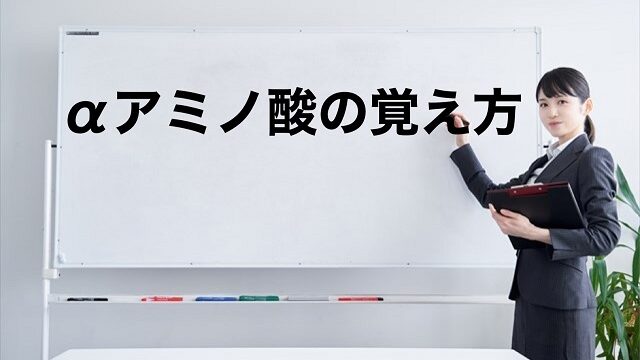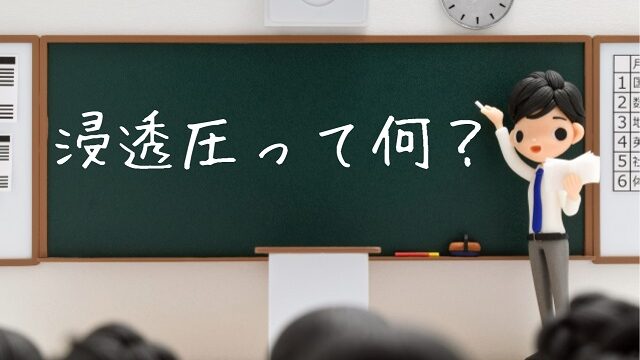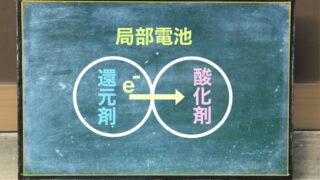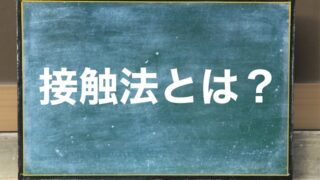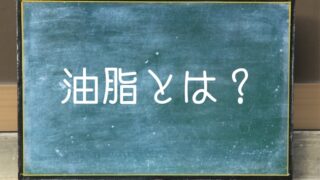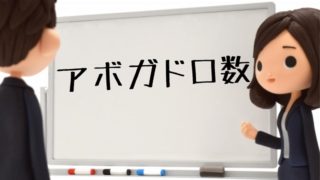今回の記事では高校化学で学習する
ハーバーボッシュ法のすごさについてわかりやすく解説します。
【高校化学】ハーバーボッシュ法のすごさ
ハーバーボッシュ法は20世紀最大の発見、
20世紀最大の人類に貢献した反応といわれています。
化学肥料を大量生産できるハーバーボッシュ法が発明されなかったら人類は人口爆発に耐えられなかったんだよね。
飢餓だけじゃなくて健康面でも屎尿を肥料に使ってたから慢性的に寄生虫に悩まされてたらしいし。 https://t.co/dv4QtHGphl— チャッピー (@junhagemay) March 10, 2022
ハーバーボッシュ法とは?
ハーバーボッシュ法は1906年に考案されたアンモニア($NH_3 $)の工業的製法です。
反応式はめちゃくちゃ簡単です。
$N_2 $+$3H_2 $⇔$2NH_3 $
中学生でも書けるようなすごく簡単な反応ですね。
これの何が20世紀最大の発見なのでしょうか?
窒素は希ガスに近いくらい反応性の低い気体です。
そんな窒素を化学反応させてアンモニアを作るというのはすごく大変なことです。
つまり、反応性の低い窒素を反応させることに
ものすごい苦労があったわけです。
この生物の存在はめちゃくちゃ大事。こいつらいなかったら自然界での窒素利用は一気に難しくなる。
なんたって窒素は希ガスに次いで反応性が低いんだから。 https://t.co/idWNpxeqm5— 吉田ヒロアキ (@Yoshida_gakusyu) November 25, 2020
では反応を可能にするためにはどんな工夫をしているのでしょう?
まず、触媒として鉄($Fe $触媒)を使います。
触媒というのは反応を起こりやすくするために加えるもののことです。
ですが、値段が高い触媒だと意味がありません。
アンモニアソーダ法は工業的製法です。
大量生産して、誰かに売ってお金を儲ける製法のことです。
⇒工業的製法とは?わかりやすく解説
なので、値段が高い触媒だと製造コストが高くつくため、
儲けが減ってしまいますからね。
ですが、鉄はそんなに高い金属ではありません。
だから鉄を触媒として使うことができました。
これもアンモニアソーダ法のすごいところです。
ですが、鉄さえあればすぐに反応するわけではありません。
窒素はそれくらい安定していますから。
・高温(400~600℃)
・高圧(200~1000気圧)
という条件が必要です。
高圧にするには圧力に耐えるだけの
頑丈な容器が必要になります。
アンモニアを工業的に工場で大規模で作るには
ものすごく頑丈な容器が必要なのです。
何度も何度も容器が破裂するような失敗があったそうです。
いろんな実験を繰り返してやっとアンモニアの大量生産につながったそうです。
ハーバーボッシュ法、圧縮機はまぁなんとかなるにしても材料が死ぬほど厄介で、高温高圧環境で水素とか扱うから部材に鋼鉄とか使うと脆化が起きるんですよ。
— ろくせいらせん (@dddrill) May 5, 2021
「50 ℃未満で水素と窒素からアンモニアを合成できる触媒の開発に初めて成功」(東工大)
これはすごい、ハーバーボッシュ法は高温・高圧でやる必要があるから大量のエネルギーを必要とするけど、この触媒が実用化されたら自然エネルギーのみでアンモニア合成する道が拓けそうhttps://t.co/QjzMw8ceHp
— T前 (@ohmurata) April 28, 2020
ハーバーボッシュ法の何がすごいの?
そもそも論としてアンモニアを大量に作ったとして
何の利点があるのでしょう?何がすごいのでしょう?
アンモニアは汚いトイレで漂っている気体じゃないですか。
刺激臭がすごいですね。
#柔軟剤 でも #刺激臭 みたいなのあるけどあれはなんなんだ、理科の実験で使ったアンモニア臭の刺激臭を思い出す。もう単なる #公害
まだ鼻の奥に僅かながら微量の臭いが残ってるから鼻うがいしてみる。#香害 と #コロナ 対策ほぼ同じ #香害は公害 #コロナウィルス #マイクロカプセル に付着しないの?— あさいん (@ocka_ocikca_) May 1, 2020
可愛い可愛いタイ古式マッサージの教え子ちゃんが「先生、卒業おめでとうございます」って持って来てくれました🥺
だから苦手な匂い聞かれたのか。
「刺激臭、アンモニア臭」って答えたら「それ、好きな人いないですよw」って言われました。㊗️ pic.twitter.com/KWhKH6ljpb— マナミ🌸鍼灸✖️東洋✖️タイ古式マッサージ (@thai_ken_jo) March 12, 2022
そんなアンモニアを作って何のメリットがあるのでしょう?
何がすごいのでしょう?
そもそもハーバーボッシュ法はノーベル賞をとっている手法ですからね。
ここがすごいですよね。
個人的にハーバーボッシュ法の発明はノーベル賞の中でも屈指のレジェンド級だと思っていて、人類を救済した発明だと思っています。
— 蛸島ルル家 (@fuyukoji) December 14, 2021
ハーバー博士って、ハーバーボッシュ法のあの!
ノーベル賞まで取ってたのか#新映像の世紀— 𝐘𝐔𝐓𝐎 (@hinahinata1110) December 20, 2021
ハーバーボッシュ法でできたアンモニア。
$N_2 $+$3H_2 $⇔$2NH_3 $
これに$NNO_3 $(硝酸)と反応させたら$NH_4Cl $
$HCl $(塩酸)を加えると中和反応により$NH_4NO_3 $(硝酸アンモニウム)になります。
$H_2SO_4 $(硫酸)と反応させたら$(NH_4)_2SO_4 $(硫酸アンモニウム)になります。
上記3つはアンモニアが酸と反応してできるアンモニウム塩なのですが、
いずれも植物の肥料として利用できるのです。
つまり、ハーバーボッシュ法は肥料の原料となるアンモニアを大量に作ることを
可能にした方法といえます。
では肥料が大量生産できたら何が可能になりますか?
高校?の化学の授業で習った『ハーバーボッシュ法』
アンモニアを沢山作れる様になる→肥料が作れる→飯が沢山食える→人口が爆発的に増加
アンモニア製造の技術も難しいが何よりその技術に耐え得る設備がなく、それを作ったのが世界のBoash創立者一族
この事実を知ると欧州の歴史の厚みを感じる pic.twitter.com/nNxyQrUvPi
— そーなんだ化学 (@bouekidoctor) October 30, 2020
肥料が大量に作れるということは食物である小麦などの栽培量が大幅にアップするわけです。
小麦の栽培効率がアップするわけですよ。
そして小麦が大量生産されるということは、
最終的に食料であるパンの大量生産が可能になります。
ひよこ
↑
飼料の小麦とか大豆とか
↑
窒素含有化学肥料
↑
ハーバーボッシュ法結論:ひよこは工業製品
— su (@spoon_C_) December 7, 2020
原料となる窒素は空気中に入っているものです。
それがアンモニアになって肥料になって小麦になり、
最後、パンになって帰ってくるわけですね。
空気からパンを作ることができるということです。
空気から小麦を作るハーバーボッシュ法(空気窒素の固定化)
空気から小麦を作る、が比喩でなく直喩になる?
あと、体内脂肪を二酸化炭素にしてダイエット出来る研究もぜひ。 https://t.co/4JdApWhU8L
— とかげ (@tokagenokage) October 5, 2021
ということでハーバーボッシュ法はノーベル賞を受賞するわけです。
もしハーバーボッシュ法が考案されていなかったら
地球の人口は18億人くらいでストップしたといわれています。
人口を賄うだけの食料を作れなかったからです。
でも地球上の人口は約70億人くらいまで増えています。
たまーに思い出して地球の人口みると億単位で記憶と違ってびっくりする pic.twitter.com/O0PyclmdMX
— じょん (@chariyamajudo) March 9, 2022
ハーバーボッシュ法の貢献は非常に高いです。
地球上の人口を大きくしたということで画期的な製法です。
空気からパンを作るというのがハーバーボッシュ法のすごさです。
高校?の化学の授業で習った『ハーバーボッシュ法』
アンモニアを沢山作れる様になる→肥料が作れる→飯が沢山食える→人口が爆発的に増加
アンモニア製造の技術も難しいが何よりその技術に耐え得る設備がなく、それを作ったのが世界のBoash創立者一族
この事実を知ると欧州の歴史の厚みを感じる pic.twitter.com/nNxyQrUvPi
— そーなんだ化学 (@bouekidoctor) October 30, 2020
人類は70億人レベルまで増えたのは化学肥料と遺伝子改良によって収穫量が激増して食わせられるようになったからで、ハーバーボッシュ法の誕生時期の1900年では人口は十数億人とか言われとるわね。。化学肥料捨てたら、50億人くらいには餓死してもらわなアカンかも知れんゾ。
— 事務カリー(花粉症の季節) (@zimkalee) October 21, 2021
次にハーバーボッシュ法によってスポットライトが
当たるようになった工業的製法について説明します。
名前はオストワルト法といいます。
続きは次の記事で解説します。