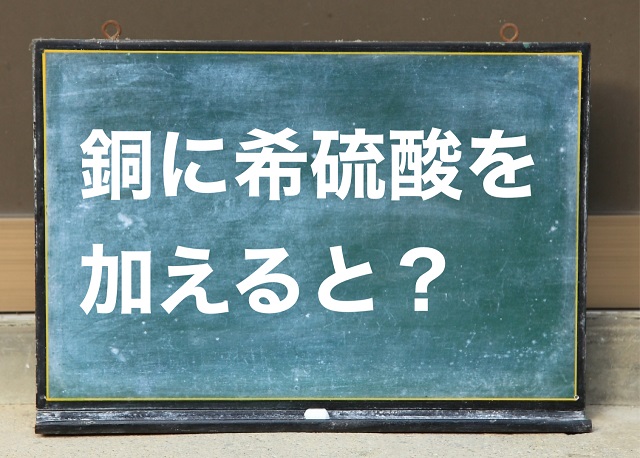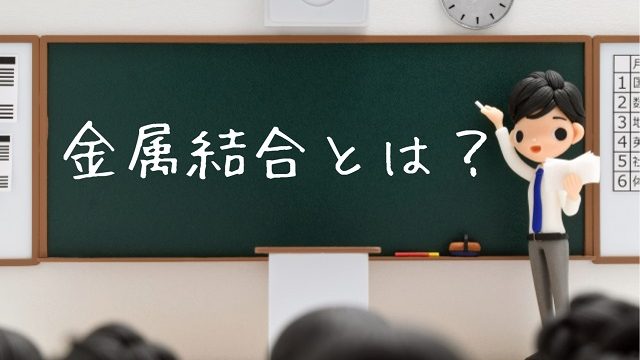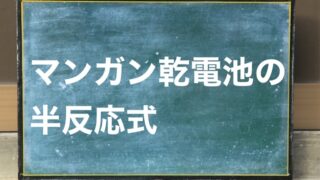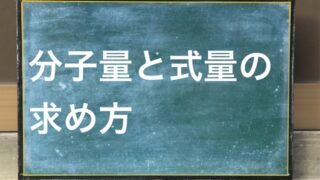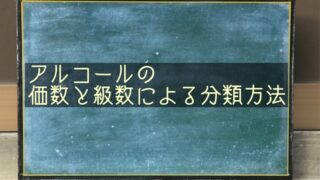この記事では銅に希硫酸を加えるとどうなるか?
解説します。
Contents
銅に希硫酸を加えると?
銅に希硫酸を加えるとどうなるのでしょう?
まず大前提として、酸化還元反応式とイオン化傾向の理解が必須です。
なので今回の記事を読んでよくわからなかった方は
以下の記事を読んでから、また今回の記事に戻ってきていただけるとうれしいです。
では本題に入っていきましょう。
まずイオン化傾向を考えましょう。
イオン化傾向は水素H>銅Cu
ですよね。
よくわからない方はこちらをご覧ください。
⇒イオン化傾向が大きいほど何がいえるか?
大丈夫でしょうか?
銅と希硫酸です。
前回解説したように
希硫酸は酸ですからイオン反応式を示すときには
$H^{+} $になりますね。
なのでイオン反応式の左辺は
$Cu $+$H^{+} $
となります。
そして銅と水素を比べると水素の方がイオン化傾向が大きいです。
なので水素の方がイオンになりやすいです。
イオンになりやすい方がイオンになります。
ということは左辺が$Cu $+$H^{+} $であることから
反応しないということです。
$Cu $+$H^{+} $⇒反応しない
です。
わかりますか?
反応というのは、あるべきすがたでないからあるべき姿に向かうのです。
だから反応するのです。
初めからあるべき姿であるなら反応しようがありません。
つまり銅は希硫酸には溶けないということです。
なぜなら銅と水素を比べたら水素の方がイオン化傾向が大きいからです。
どうすれば銅が溶けるの?
このやっかいな銅を無理やり溶かそうとしたら
どうすればよいのでしょう?
銅を溶かすには普通の酸ではダメです。
酸化作用のある酸でないと銅は溶けません。
そしてこのとき発生する気体は水素ではありません。
当たり前ですよね。
だって
$Cu $+$H^{+} $⇒反応しない
のように$H^{+} $のままだからです。
$H^{+} $が反応しないのに水素が出たらおかしいですよね。
酸化作用のある酸というのは非常にわかりにくい言葉です。
わかりやすくいうと酸化作用のある酸とは電子を奪う性質のある酸のことです。
具体的には熱濃硫酸とか硝酸が酸化作用のある酸に含まれます。
熱濃硫酸というのは銅の中に濃硫酸を入れて加熱するとできます。
熱い濃硫酸を銅の中に入れるのではありません。
そんなことしたら危険極まりないからです。
金属を溶かすためには電子を奪ってイオンにしてしまえば溶けます。
これはこちらの記事で解説しています。
⇒イオン化傾向が大きいほど何がいえるか?
だから電子を奪う性質のある酸だと
銅の電子が奪われてイオンになって溶けるわけです。
話を元に戻します。
銅の中に濃硫酸を入れて加熱すると(熱濃硫酸になると)、
銅が溶け、$SO_2 $(二酸化硫黄)ができます。
それから硝酸($HNO_3 $)は薄い場合(希硝酸)と濃い場合(濃硝酸)で
反応式が変わってきます。
希硝酸の場合は銅が溶けて$NO $ができます。
濃硝酸の場合は銅が溶けて$NO_2 $ができます。
とにかく銅との反応において水素は絶対に出ないということは
覚えておきましょう。
以上で解説を終わります。