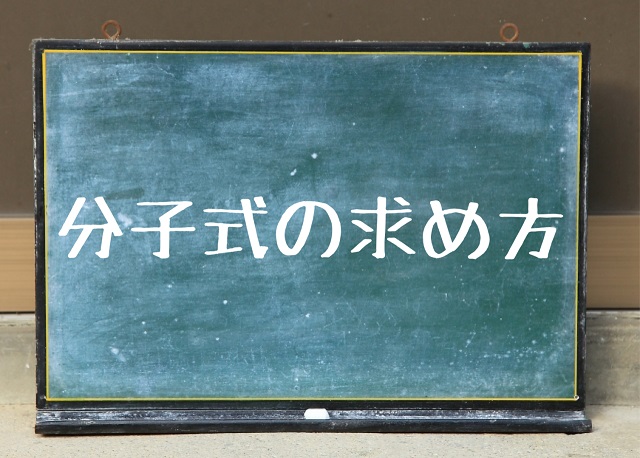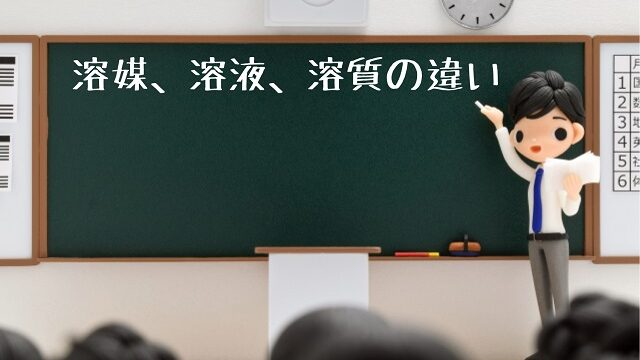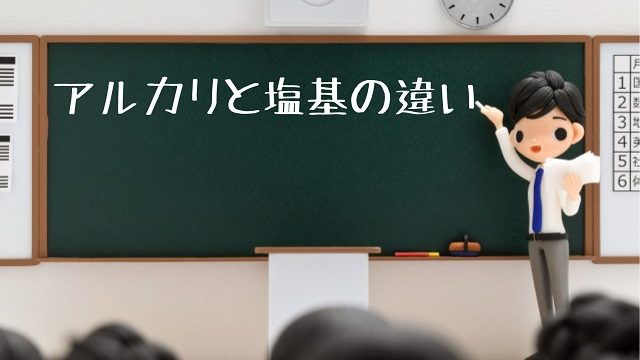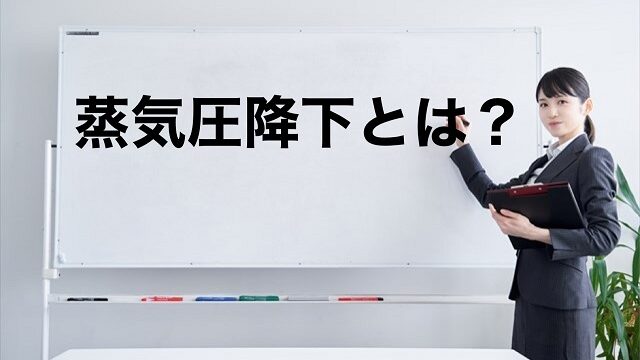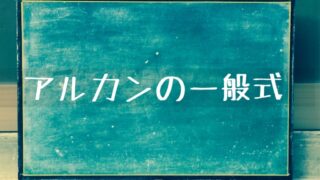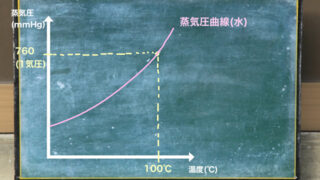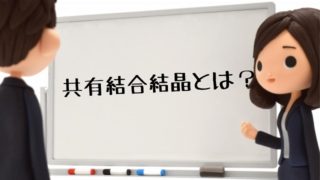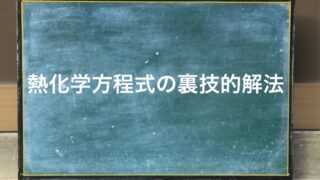この記事では例題を説きながら
分子式の求め方について解説していきます。
そもそも分子式って何か?
わからないという方は、先にこちらの記事をご覧ください。
⇒構造式・示性式・分子式・組成式の違いを酢酸を例にわかりやすく解説
分子式の求め方
まず具体例として
示性式・・・$CH_3COOH $
分子式・・・$C_2H_4O_2 $
となります。
分子式って$C_2H_4O_2 $みたいな式のものをいいます。
分子式の求め方(例題)
炭素C、水素H、酸素Oからなる有機化合物Xがあったとしましょう。
例題として有機化合物Xは8.8グラムだったとしましょう。
この有機化合物を完全燃焼させます。
すると気体が発生しますから、それをきちんと調べます。
有機化合物XはC、H、Oからできています。
例えば炭素Cが完全燃焼したらどうなるでしょう?
二酸化炭素$CO_2 $が発生しますね。
不完全燃焼だったら一酸化炭素$CO $ができますが、
完全燃焼なので一酸化炭素はできません。
二酸化炭素$CO_2 $だけできます。
炭素が完全燃焼するときの熱化学方程式は次の通りである。
C + O2 = CO2 + 393.9kJ
— 快速ジャガビー (@jkabasawa17) March 13, 2021
それから水素Hが燃えたらどうなるでしょう?
水素Hが燃えたら水$H_2O $ができます。
では酸素Oが燃えたら?
酸素は燃えません。
酸素Oは水素を燃やしてできた水$H_2O $であったり
炭素を燃やしてできた二酸化炭素$CO_2 $の原料になっています。
酸素は燃えない【定期】
— しらす (@sirasu314) March 7, 2021
こんな感じで酸素Oは二酸化炭素や水に入っています。
だから二酸化炭素や水に入ってしまうのです。
ということで有機化合物Xを燃やすと二酸化炭素と水は発生するということになります。
そして有機化合物X8.8グラムを燃やしたら
二酸化炭素が17.6グラム発生したとしましょう。
水は7.2グラム発生したとします。
ところで二酸化炭素$CO_2 $の分子量は炭素の原子量が12で酸素が16なので44です。
分子量がわからない方はこちらの記事をご覧ください。
⇒分子量と式量の求め方
分子量が44の二酸化炭素が17.6グラム入っていて、
炭素の原子量が12なので、
炭素の質量は17.6×12/44という式で表すことができます。
二酸化炭素の分子量は44で
炭素はその中で12しかありません。
なので、二酸化炭素17.6グラム中に12/44という割合の炭素が含まれているため
炭素の質量は17.6×12/44という式が成り立ちます。
17.6×12/44を計算すると4.8になりますね。
17.6×12/44=4.8
それから水素Hの質量はどうなるでしょう?
水$H_2O $の分子量は水素の原子量が1で酸素が16なので18です。
よって水$H_2O $の質量は7.2×2/18
となります。
分子の2は原子量1の水素が2個あるからです。
水$H_2O $の分子量が18であっても
その中の水素は原子量が1で2ついますから2なわけです。
7.2×2/18=0.8
となります。
・炭素Cの質量は4.8グラム
・水素Hの質量は0.8グラム
では酸素Oはどうなるでしょう?
酸素は$H_2O $や$CO_2 $から求めたらだめです。
どうしてでしょう?
なぜなら$H_2O $や$CO_2 $に入っている酸素は一部だからです。
$H_2O $や$CO_2 $に存在する酸素は燃やすために利用された酸素にすぎません。
あくまで一部です。
燃やすために外から入ってきた酸素です。
いくらそこに酸素を含む有機化合物Xがあっても
その場所(空気中)に有機化合物X以外の酸素がないと完全燃焼しません。
だから、完全燃焼してできた$H_2O $や$CO_2 $の中にも
有機化合物Xに存在した酸素Oは含まれているものの
他にも空気中の酸素O『も』含まれてしまっているのです。
・有機化合物X中の酸素
・空気中の酸素(燃やすために加えた酸素)
の両方が含まれてしまっているということです。
だから燃やすために加えた酸素も含まれてしまっているわけです。
わかっていただけたでしょうか?
ということは$H_2O $や$CO_2 $から酸素を求めたら
不正解になってしまうということですね。
$H_2O $や$CO_2 $から酸素の値を求めたらいけない
ではどうやって酸素の質量を求めたらよいのでしょう?
酸素は有機化合物Xの8.8グラム
というところを利用します。
有機化合物Xは全部で8.8グラムです。
炭素C、水素H、酸素Oを全部合わせて8.8グラムということです。
そしてここまで計算してきたように
炭素Cの質量は4.8グラム、水素Hの質量は0.8グラムでしたね。
炭素の質量4.8グラムと水素の質量0.8グラムを
全体の8.8グラムから引き算した値が酸素の質量ということです。
有機化合物Xの質量から炭素と水素の質量を引いたもの
ということで
酸素の質量は8.8ー(4.8+0.8)=3.2グラム
ということです。
・有機化合物Xの質量:8.8グラム
・炭素Cの質量は4.8グラム
・水素Hの質量は0.8グラム
・酸素Oの質量は3.2グラム
ということです。
そしたら
C、H、Oのmol比を求めましょう。
mol比は数の比率です。
数の比率は化学では一般的にmol比(モル比)で計算します。
⇒モル比についてはこちらで解説しています
まず、
・炭素Cの質量は4.8グラム
・水素Hの質量は0.8グラム
・酸素Oの質量は3.2グラム
とわかりましたね。
これを原子量で割ったらモル(mol)になります。
たとえば炭素のモル数は質量が4.8で原子量が12なので
4.8/12=0.4molです。
C:H:O=4.8/12:0.8/1:3.2/16
=0.4:0.8:0.2
=2:4:1
となりますね。
有機化学ではこうやって計算していきます。
C:H:O=2:4:1
なので、CとHとOが2:4:1の比率で入っていることがわかったのだえ
$C_2H_4O $だとわかりました。
ただこれは組成式であって分子式ではありません。
有機化学では組成式のことを実験式ということもあります。
なぜなら実験的に燃やして得られた式だからです。
とりあえず組成式はでました。
次は分子量(重さ)を求めます。
これにはいろんな方法があります。
例えば分子量が小さければ蒸発させ
気体の状態方程式に代入して分子量を求める方法があります。
⇒理想気体の状態方程式をわかりやすく導出してみた!
あるいは分子量が大きいものはベンゼンなどに溶かします。
ベンゼンなどに溶かすと凝固点が下がります。
下がり具合から分子量を求める方法もあります。
⇒凝固点降下の原理と身近な例
こんな感じでいろんな方法で分子量を求めることができます。
例えばXの分子量が実験で132だったとしましょう。
先ほど組成式を求めました。
Xの組成式は$C_2H_4O $だったので分子量(正式には式量)は44です。
(炭素の分子量12、酸素の分子量16、水素の分子量は1だから)
⇒分子量と式量の求め方
Xの分子量は132で組成式から得られた式量は44だから
実際の分子量は3倍ですね。
なぜなら132÷44=3だからです。
ということなので組成式$C_2H_4O $を3倍すればよいわけです。
すると$C_6H_{12}O_3 $
だとわかりました。
これが分子式です。
よってXの分子式は$C_6H_{12}O_3 $でした。
さらに研究であれば
実験を加えて性質を確かめていきます。
たとえば酸性だとわかったら『カルボキシル基』があるとか。
そうやって最後に構造を決めていきます。
有機化学の目的というというのは
構造式を決めるのが最終目標です。
⇒構造式・示性式・分子式・組成式の違いを酢酸を例にわかりやすく解説
ですが、材料がわからなければ構造もへったくれもありません。
だからまずは分子式を求めることが先です。
そのあと、酸性とかアルカリ性などの性質を調べて
最終的に構造式を決めるということです。
なのでまず分子式を求めるということは非常に重要です。
以上で解説を終わります。