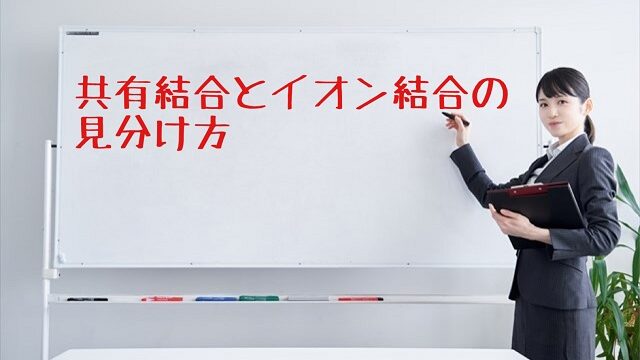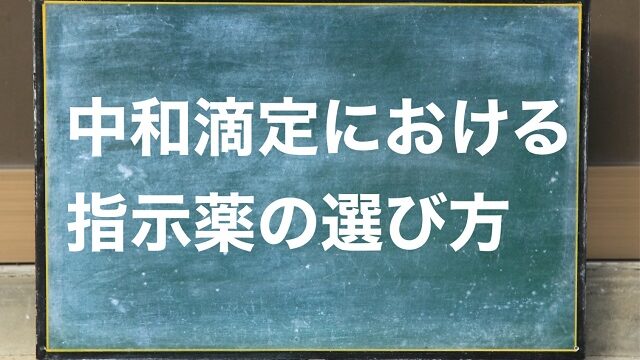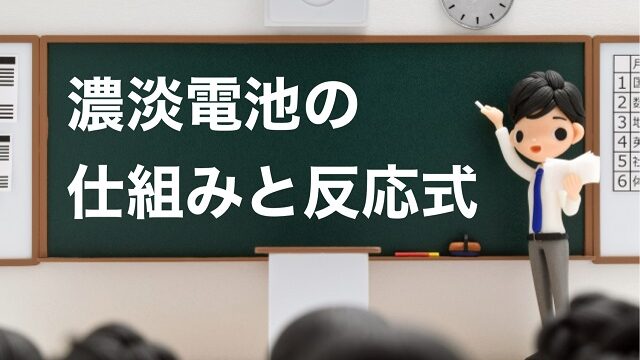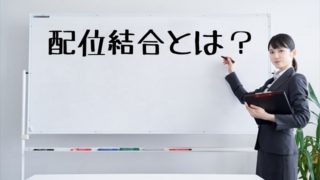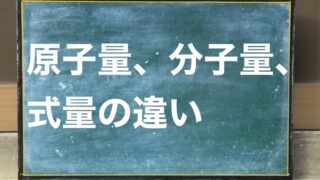気体定数を暗記で対処しようとしている方は多いです。
気体定数とかファラデー定数って暗記事項?
— こくりつこうえんぷらす (@Nationalparkplu) May 20, 2022
これは悪いことではないと思います。
私も獣医大学受験時代は暗記で対応しましたし。
⇒当ブログ管理人のプロフィール
でも、気体定数の導き方を知っていれば
覚えることが1個減ります。
より試験に出るところを暗記するためにも
そんなに重要でない気体定数については理解で対処したいところです。
そこで今回の記事では気体定数の求め方についてわかりやすく解説していきます。
気体定数の求め方をわかりやすく説明します
0℃、1気圧(atm)を標準状態といいます。
標準状態の意味はこちらで詳しく解説しています。
⇒1モルから得られる3つの情報とは?わかりやすく解説
0℃・1気圧の気体状態を標準状態と呼ぶ。
この標準状態において理想気体1molの占める容積は22、4Lである。
— 未知なる人間、遥かなる宇宙☀ (@Orion_G7) May 20, 2022
標準状態で1モル(気体の種類によりません)の気体は22.4Lを占めます。
この22.4Lは暗記事項です。
22.4Lの覚え方はこちらの記事で詳しく解説しています。
⇒3つのモル公式の覚え方をわかりやすく解説
ところで気体の状態方程式はPV=nRT
ですよね。
気体の状態方程式
気体定数の定義より、PV/T=Rである。
この式は気体1molのとき成り立ち、気体の体積は同温同圧なら物質量に比例するので、気体nmolにおいて、
PV/T=nR、すなわちPV=nRTが成り立つ。この式を気体の状態方程式という。— 大学受験化学bot (@jukenkagaku) May 21, 2022
圧力Pは1気圧で体積は22.4L,標準状態なのでn=1mol(モル)、
Rは今回求める気体定数なのでそのままR、Tは絶対温度なので、普通の℃に273を足します。
0℃に273を足すと273Kになります。
T(ケルビン、K)=t(℃)+273
です。
なので―273℃は絶対零度(-273℃+273=0K)です。
ここで気体の分子運動は止まってしまいます。
なので気体の体積は消えてしまいます。
だから―273℃以下はありません。
よってPV=nRTに上記数字を代入すると
1×22.4=1×R×273
となりますね。
よってR=22.4÷273=0.082
となり、気体定数Rは0.082だとわかりました。
化学の気体定数と物理の気体定数は違う?
ちなみに物理における気体定数は圧力の単位が違います。
物理の場合の圧力はN(ニュートン)/$m^{2} $ですし
体積も$m^{3} $です。
今回解説した化学の場合、圧力はatm(アトム)ですし
体積はL(リットル)です。
以上を元に物理の場合の気体定数を求めると8.31となります。
なので、化学にいう気体定数と物理でいう気体定数は
同じものを扱っていますが、単位が違うから数値が違います。
そんなことなので、化学で計算した気体定数を
物理の熱力学などで使用するとおかしな数値になるのでやめましょう。
気体定数の求め方まとめ
化学の問題では気体定数R=0.082を
そのまま書いてくれていることが多いです。
でも、今回解説したように気体定数は導き出すことができます。
以上参考にしていただけるとうれしいです。