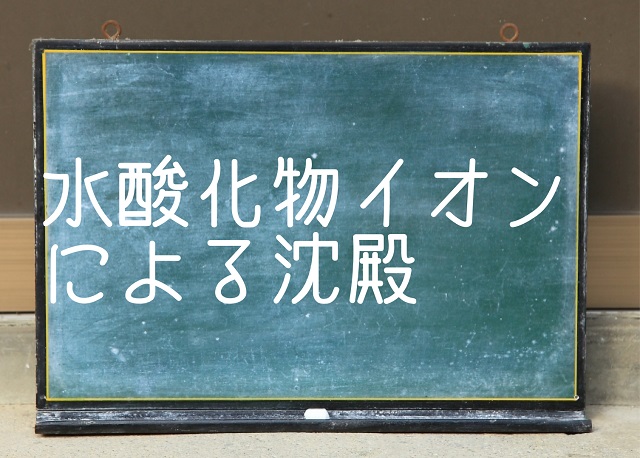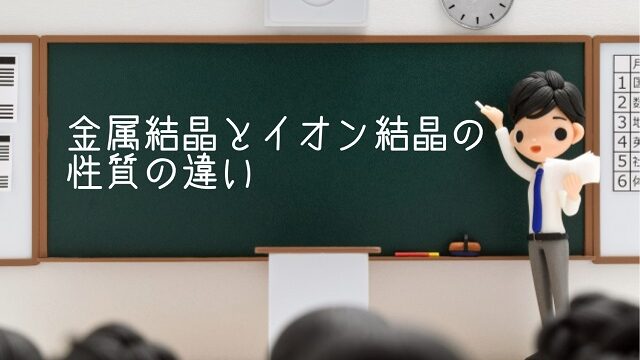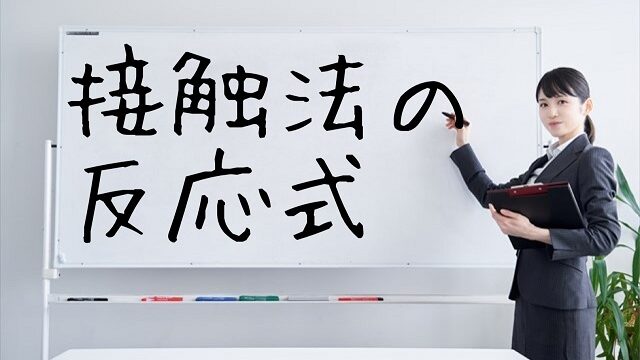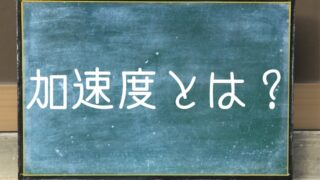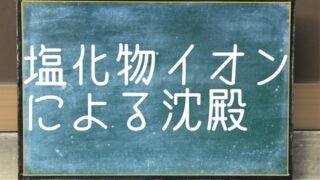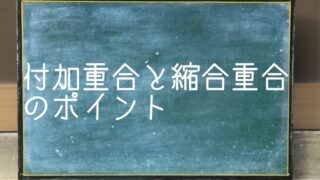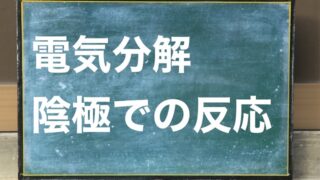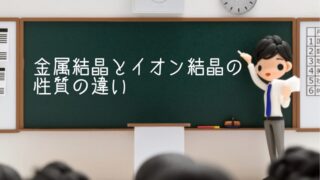この記事では$OH^{ー} $(水酸化物イオン)による沈殿について
わかりやすく解説していきます。
Contents
水酸化物イオンによる沈殿
$OH^{ー} $(水酸化物イオン)は塩基性ですよね。
使う試薬が決まっています。
水酸化ナトリウム($NaOH $)です。
水酸化ナトリウムは水に溶け電離します。
電離=イオンに分かれるってことです。
なので
$NaOH $⇒$Na^{+} $+$OH^{ー} $
となります。
そしてアンモニア水。
これは弱塩基でしたね。
アンモニア水は弱塩基で
$NH_3 $+$H_2O $⇔$NH_4^{+} $+$OH^{ー} $
となります。
$NaOH $⇒$Na^{+} $+$OH^{ー} $
$NH_3 $+$H_2O $⇔$NH_4^{+} $+$OH^{ー} $
どちらも$OH^{ー} $(水酸化物イオン)が出ています。
だから塩基性です。
他にも塩基性の物質はいっぱいあります。
ですが、塩基性で沈殿の話になると
$NaOH $⇒$Na^{+} $+$OH^{ー} $
$NH_3 $+$H_2O $⇔$NH_4^{+} $+$OH^{ー} $
の2つだけになることが多いです。
ここまでを踏まえて沈殿について考えていきましょう。
アルミニウムイオンと水酸化物イオンにおける沈殿
まず$Al^{3+} $(アルミニウムイオン)から。
$Al^{3+} $(アルミニウムイオン)が溶けている水溶液に
$NaOH $⇒$Na^{+} $+$OH^{ー} $
$NH_3 $+$H_2O $⇔$NH_4^{+} $+$OH^{ー} $
のどちらかの水溶液を加えます。
するとどちらにも$OH^{ー} $(水酸化物イオン)がありますから
$Al^{3+} $+$3OH^{ー} $⇒$Al(OH)_3 $↓(白色)
となります。
上記のように$Al(OH)_3 $↓になり白色の沈殿ができます。
上記反応式をみてピンときますか?
電気が0になっていますね。
左辺を見ると
$Al^{3+} $+$3OH^{ー} $となっています。
$Al^{3+} $が3+で、$3OH^{ー} $がー1×3で3-なので
電気がちょうど0になります。
何がいいたいか?というと
電気を持っていたら溶けるってことが言いたいのです。
つまり溶けない(沈殿する)ということは
電荷がちょうど打ち消しあってしまうということです。
だから沈殿を考えるときは
電気(=電荷)が0になるように考えればよいのです。
話を元に戻します。
$Al^{3+} $は2段構えです。
$Al^{3+} $+$3OH^{ー} $⇒$Al(OH)_3 $↓(白色)
で話が終わりではありません。
上記式みたいに白色の沈殿ができた状況なのに
さらに
$NaOH $⇒$Na^{+} $+$OH^{ー} $
$NH_3 $+$H_2O $⇔$NH_4^{+} $+$OH^{ー} $
のどちらかを過剰に加えます。
すると溶ける場合があるのです。
例えば$Al(OH)_3 $↓(白色)が沈殿したたあと
さらに$NaOH $(水酸化ナトリウム)を加えていくとしましょう。
すると以下のようなものができます。
$Al(OH)_3 $+$OH^{ー} $⇒$AlO_2^{ー} $(アルミン酸イオン)+$H_2O $
アルミン酸イオン($AlO_2^{ー} $)ができて溶けてしまうんです。
つまり、最初、$NaOH $を加えて$Al(OH)_3 $↓(白色)が沈殿して
さらに$NaOH $を加え続けるとせっかくできた沈殿が溶けてしまうってことです。
こんな感じで二段構えの反応が起こります。
いったん沈殿するのは当たり前。
さらに過剰に加えると溶けるのです。
溶けてできたアルミン酸イオン($AlO_2^{ー} $)をよく見てください。
1価の陰イオンになっていますね。
『電荷を持っているイオン=溶けている』ってことです。
アルミン酸イオン($AlO_2^{ー} $)は溶けていて透明です。
$Al(OH)_3 $↓は白色だったのに不思議ですね。
先ほどは$Al(OH)_3 $↓の沈殿に対しさらに
$NaOH $(水酸化ナトリウム)を加えたパターンでした。
では$Al(OH)_3 $↓の沈殿に対しさらに
アンモニア水(NH_3 $)を過剰に加えたらどうなるでしょう?
結論は溶けません。
不思議ですよね。
(1)$Al^{3+} $に$NaOH $(水酸化ナトリウム)か$NH_3 $(アンモニア水)を加える
⇒$Al(OH)_3 $↓の白色の沈殿ができる。
(2)$Al(OH)_3 $↓の白色の沈殿にさらに過剰に$NaOH $を加える
⇒アルミン酸イオン($AlO_2^{ー} $)になって溶ける(透明)
でも、$Al(OH)_3 $↓の白色の沈殿にさらに過剰にNH_3 $(アンモニア水)を加える
⇒溶けない
ということです。
亜鉛イオンと水酸化物イオンにおける沈殿
$Zn^{2+} $に$NaOH $(水酸化ナトリウム)か$NH_3 $(アンモニア水)を加えると
$Zn(OH)_2 $↓の白色の沈殿ができます。
アルミニウムの時と同様に$Zn(OH)_2 $↓の白色の沈殿に対して
さらに$NaOH $(水酸化ナトリウム)か$NH_3 $(アンモニア水)を加えると・・・
どちらも溶けてイオンになります。
ただし、
$NaOH $(水酸化ナトリウム)を過剰に加えると
亜鉛酸イオン($ZnO_2^{2ー} $)になり、
$NH_3 $(アンモニア水)を過剰に加えると錯イオン(【$Zn(NH_3)_4】^{2+} $)になって溶けます。
そして錯イオン(【$Zn(NH_3)_4】^{2+} $)の形は正四面体になります。
アンモニアが4つ配位するのですが、正四面体型に配位をするのです。
鉄イオンと水酸化物イオンにおける沈殿
それからFe(鉄)には$Fe^{2+} $と$Fe^{3+} $があるのですが
どちらが有名か?というと$Fe^{3+} $の方です。
なので$Fe^{3+} $と水酸化物イオンの沈殿について解説します。
$NaOH $(水酸化ナトリウム)か$NH_3 $(アンモニア水)を$Fe^{3+} $に加えることで
$Fe(OH)_3 $↓となり、赤褐色の沈殿ができます。
では$Fe(OH)_3 $↓という沈殿ができた後、
さらに過剰に$NaOH $(水酸化ナトリウム)か$NH_3 $(アンモニア水)を加えると
どうなるのでしょう?
結論としてはどちらを過剰に加えても解けません。
沈殿ができたままです。
ちなみに$Fe^{2+} $の場合も結論は同じです。
$Fe^{2+} $に$NaOH $(水酸化ナトリウム)か$NH_3 $(アンモニア水)を加えてできた
$Fe(OH)_2 $↓は薄い緑色の沈殿ができます。
$Fe(OH)_2 $↓にさらに過剰に$NaOH $(水酸化ナトリウム)か$NH_3 $(アンモニア水)を加えても解けません。沈殿ができたままです。
銅イオンと水酸化物イオンにおける沈殿
$Cu^{2+} $(銅イオン)に$NaOH $(水酸化ナトリウム)か$NH_3 $(アンモニア水)を加えると$Cu(OH)_2 $↓(水酸化銅)の青白色の沈殿ができます。
水酸化銅だって pic.twitter.com/zrKgxQQjNj
— アデリー (@7pengnta) May 27, 2021
$Cu(OH)_2 $↓(水酸化銅)の青白色の沈殿に対して
さらに過剰に$NaOH $(水酸化ナトリウム)か$NH_3 $(アンモニア水)を加えると
どうなるでしょうか?
$NaOH $(水酸化ナトリウム)は沈殿のままで溶けません。
$NH_3 $(アンモニア水)過剰の場合には
錯イオン【$Cu(NH_3)_4】^{2+} $を作ります。
【$Cu(NH_3)_4】^{2+} $は要注意です。
名前はテトラアンミン銅(Ⅱ)イオンといいます。
テトラはテトラポッドのテトラで4という意味です。
なのでテトラアンミンでアンモニアが4つという意味だとわかりますね。
また$Cu^{2+} $(銅イオン)は2価の陽イオンだから銅(Ⅱ)イオンです。
つなげて【$Cu(NH_3)_4】^{2+} $は
テトラアンミン銅(Ⅱ)イオンと読みます。
テトラアンミン銅(Ⅱ)イオンは濃青色をしていて
形は正方形です。
亜鉛の場合と違いますね。
【$Zn(NH_3)_4】^{2+} $の場合は正四面体でしたからね。
同じアンモニアが4つであっても
形がまったく違います。ご注意ください。
銀イオンと水酸化物イオンにおける沈殿
銀の場合水酸化銀は不安定です。
$NaOH $(水酸化ナトリウム)か$NH_3 $(アンモニア水)を
加えると酸化銀($Ag_2O $)が沈殿します。
褐色の沈殿です。
褐色というのは茶色のことです。
化学では茶色って言葉を使いません。
褐色という言葉を使います。
化学だと「茶色」も使われないです いろんな色のお茶があるからです
日本人が茶色と聞いて想像するブラウンは化学では「褐色」っていいます!
— なぎの (@makonagix) October 24, 2022
酸化銀($Ag_2O $)の沈殿に対してさらに過剰に
$NaOH $(水酸化ナトリウム)か$NH_3 $(アンモニア水)を加えると
どうなるでしょう?
$NaOH $(水酸化ナトリウム)を過剰に加えた場合は何も起こりません。
沈殿のままです。
$NH_3 $(アンモニア水)を過剰に加えると
【$Ag(NH_3)_2】^{+} $という錯イオンができて溶けます。
【$Ag(NH_3)_2】^{+} $は
NH_3が2つしかないので立体になりません。直線形になります。
$NH_3 $(アンモニア水)を過剰に加えてできた錯イオンは
きちんと形をチェックしておきましょう。
ここまで解説したものは覚えておきましょう。
次は硫化物イオンによる沈殿について解説します。
⇒硫化物イオンによる沈殿重要ポイントをわかりやすく解説